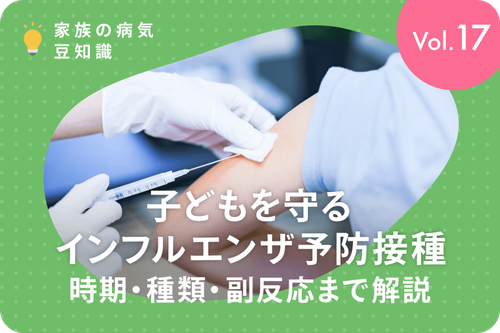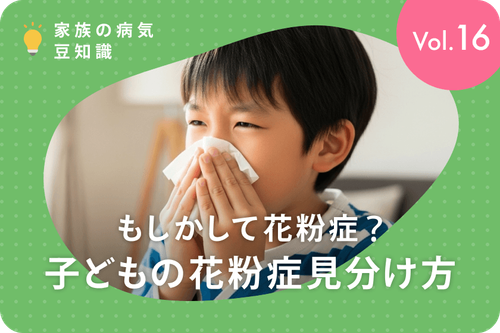2023.12.21
病気知識
アデノウイルスについて
慶應大学病院 小児科専門医 中村先生がよくある質問にお答えします
実は一年中感染する恐れのあるアデノウイルス。51種の感染型があるため、免疫がつきにくく何度も感染する可能性があります。夏と冬に流行のピークが見られ、地域によっては現在も流行が続いています。特に、今年は大流行しており、お子さんも、親御さんも、小児科医までもがアデノウイルスに苦しめられています。今回は改めて、お子さんが感染したときの対応方法、登園の目安、親御さんからのよくある質問にお答えします。

どんな病気?
アデノウイルスに感染することで発症します。ヒトに感染するアデノウイルスの型は51種類あり、感染する型によって症状が異なります。
アデノウイルスによる感染症としては、大きく4種類、
・急性咽頭扁桃炎、肺炎など
・咽頭結膜熱(プール熱)、流行性角結膜炎(流行り目)
・胃腸炎
・出血性膀胱炎
があります。
アデノウィルス感染症は以前は夏に多い感染症でした。しかし現在は、夏だけでなく一年を通して感染することが知られています。一年の中では特に夏と冬に流行のピークが見られています。
感染力が非常に強く、学校保健法で登園や登校が禁止となる伝染病のひとつです。特に子どもが感染しやすいので、注意が必要です。
どんな症状が出るの?
ウイルスの型によってさまざまな症状を引き起こします。今年特に流行しているタイプについて詳しく説明していきます。
・咽頭扁桃炎
高熱、喉の痛み・赤み・腫れ、白苔(扁桃腺に白い膜のようなもの)が症状として知られます。
40度近い高い熱が5日〜7日にわたって続くことが最も大きな特徴です。
抗菌薬は効きません。(他のアデノウイルスによる感染症も同様)
・咽頭結膜炎(プール熱)
発熱、咽頭発赤・咽頭痛、結膜炎の3つがメインの症状です。
感染力が非常に強いので、一人でも保育園や家庭内で発生すると、大流行してしまいます。
2023年の10月以降大流行しており、日本全国で警報が出ています。
・流行性角結膜炎(はやり目)
目の赤み、眼脂(目ヤニ)、羞明(光を見ると眩しく感じる)があります。
・胃腸炎
症状として、下痢、嘔吐、発熱があります。
ロタウイルス、ノロウイルスなどの胃腸炎に比べると軽度だと言われています。
検査はどうする?
アデノウイルスが流行している時期に、高熱が続く、目の赤みがある、嘔吐・下痢がある時には小児科を受診して、アデノウイルス感染かどうかを診察・迅速検査キットを使って確認します。迅速検査は綿棒を咽頭に擦って行います。結果は5分ほどで出ます。
感染したらどうする?
アデノウイルス感染症に対する特効薬はないため、症状を和らげるための対症療法が中心となります。症状は1週間程度で自然におさまるケースがほとんどです。
ただし、以下の場合や症状が急変した際には医療機関で診察を受けましょう。
・高熱が続く
・ぐったりしている
・嘔吐が続いて水分・糖分が取れない
・尿(おしっこ)が出ない、1日2回以下
他のウイルス感染症と比較すると高熱が長く続くため、こまめな水分摂取が重要です。
熱が高く身体がつらい時には、解熱剤をうまく使用して身体を休ませ、水分・糖分の摂取を行いましょう。
咳に対しては去痰剤を使いましょう。
眼の炎症(目の赤み・目ヤニ)にはステロイド点眼薬を使用することで対処します。
ホームケアのポイント
喉の痛みが強いと、水分・食事が思うように取れなくなります。お子さんの場合は、熱が出ると不機嫌になり、普段に比べてさらに好き嫌いが強く出てしまいます。小児科医からお伝えしたいのは、ご本人が好きなものを少しずつあげてほしい、ということです。できるだけ刺激が少ない、以下のような飲料、食品を選んであげましょう。
・常温の(冷えていない)ジュース
・ゼリー
など
飲水量とともに排尿量や回数もチェックしましょう。水分が取れて排尿回数が保たれていれば、自宅での経過観察で問題ありません。
発熱時は、本人が嫌がらなければ首・わきの下・脚の付け根を冷やすのもいいでしょう。
高熱が続く場合には入浴は避け、身体を拭いて清潔を保ちながら自宅で安静に過ごすようにしましょう。
家庭内感染を防ぐには?
感染経路には【飛沫】【接触】感染があり、眼の結膜・上気道(鼻・口)から感染します。家庭内感染を防ぐために以下のポイントに気を付けましょう。
・手洗い・うがいをしっかりと行う
・タオルや食器等の共用は避ける
・感染したお子さんが触れた場所やおもちゃ等から感染してしまう可能性があるので、きょうだいが同じおもちゃで遊ぶことは避ける
・使い捨て手袋をつけてオムツを交換し、その後流水・石鹸で手洗い
・感染したお子さんの目ヤニを拭き取る時は、ティッシュペーパーや濡らしたコットンを用い、手で直接眼に触れないように注意(通常の手指消毒用アルコールの効果は低いため、十分な手洗いを行った上で使用)
登園・投稿はいつから大丈夫?
咽頭結膜熱(プール熱)の場合には解熱後2日間は出席停止です。
一般的には、発熱・結膜炎・咳嗽・咽頭痛などの症状が治まってから2日間経過し、医師の許可があれば登園・登校が可能です。
発病すると法律で登園や登校が禁止となる「学校保健法第二種伝染病」に指定されています。
教えて!中村先生~アデノウイルスについて、親御さんからよくある質問に小児科医が回答~
慶應義塾大学病院 小児科専門医 中村 俊一郎先生がよくある質問にお答えします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q:同じシーズンに何度も罹ることはありますか?
A:残念ながら、1シーズンで複数回アデノウイルスに罹ってしまう可能性はあります。アデノウイルスには50以上の異なる型があるからです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q:大人も感染しますか?
A:はい、特にお子さんと一緒にいるお母さんがうつってしまうことが多いです。お子さんが感染した時・流行中は手をきちんと洗う、目・口を手で触らない、がとても重要です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q:発熱と目ヤニや充血がある場合、小児科か眼科、どちらに行くのが良いでしょうか?
A:僕が小児科医ということもありますが、小児科の受診を勧めます。目の症状以外にも咳や喉の痛みがあることが多いからです。ただ小児科医は目薬の処方に慣れていないこともあるので、この記事を見せながら、「ステロイドの目薬が効くみたいなんですけど、、、」とお伝えいただいても良いかもしれません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q:風邪のウイルスの中でもアデノウイルスには注意するようにと聞きました。なぜでしょうか?
A:高い熱が、長く続くからです。熱の出方はインフルエンザよりも強いように思います。もちろん、後遺症を残さず治ることがほとんどなのですが、それでも熱がいつまで続くのか分からないので、看病しているお母さん・お父さんとしても苦しい時間が続くことになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q:子どもがアデノウイルスに感染してしまいました。兄弟がいるのですが、どのくらいの期間、感染に気をつけるべきですか?
A:潜伏期間は5〜7日です。症状が出る2日前から感染する可能性があり、家族内の感染を100%防ぐことは難しいかもしれません。繰り返しですが、手を洗う、目・口を手で触らないことが重要です。

2023年冬、アデノウイルスの流行がかつてないほどに広がっています。高い熱が長く続くので、看病する親御さんも不安になると思います。ただ、水分・糖分の摂取ができていれば、自然に治りますので、回復を信じて見守ってあげてほしいと思います。休むことも大事な治療です。
万が一、ぐったりが強くなる、他にも症状が出てくる時、遠慮せず受診してくださいね。
監修医師のご紹介
慶應義塾大学医学部卒、同病院 小児科
小児科専門医・小児心身医学認定医・公認心理師・出生前コンサルト小児科医
普段は大学病院で病気のお子さん、病気を抱えるお子さんのきょうだい・親御さんのメンタルヘルスケアを担当。
<子どもの心の健康>から<日本の社会を変える>を合言葉に小児科医として活動しています。
子どもも、親も、救いたい。
家族のためのオンライン診療アプリ「みてねコールドクター」
みてねコールドクターでは、24時間365日、ビデオ通話で医師の診察を受けられます。
夜間・休日に診察を受けたい、病院での長い待ち時間は子どもがぐずってしまい大変、
お薬が欲しいけど病院に行く時間がないなど、家族の病気や通院のお悩みをサポートします。
お薬はお近くの薬局、または一部エリアではご自宅での受け取りが可能です。
どうぞご相談ください。
・みてねコールドクター【オンライン診療】のご紹介
https://calldoctor.jp/news/article/50/
・どう使う?ママパパ体験談①「子どもの咳と鼻水が酷く、オンラインで診てもらいました」
https://calldoctor.jp/news/article/59/