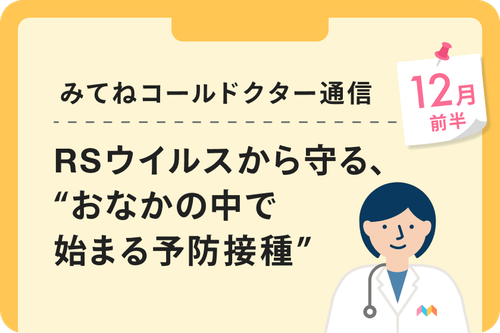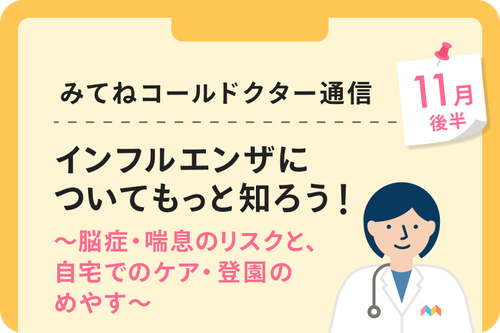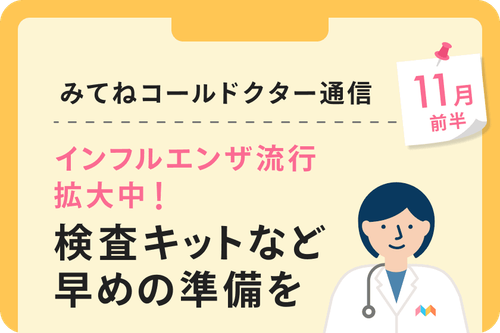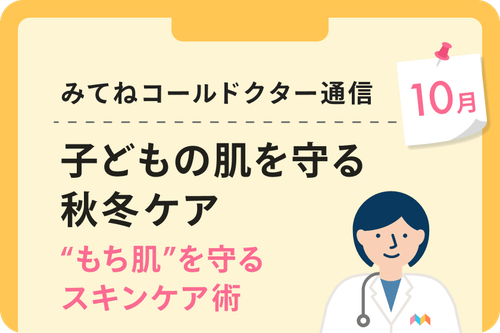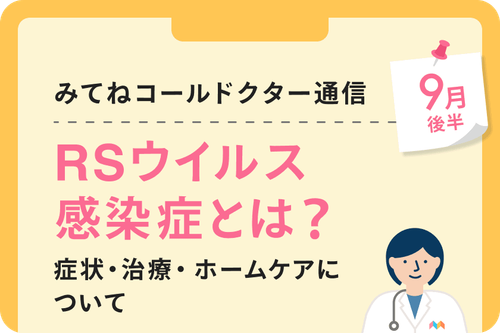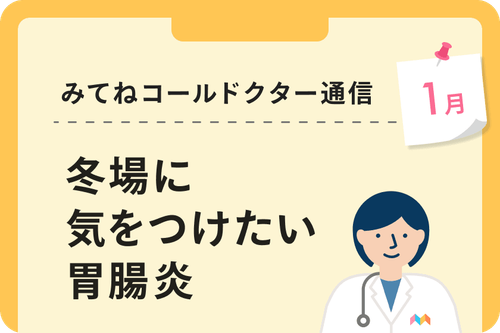
2024.01.05
ドクター通信
<みてねコールドクター通信>被災地の子どもと家族を守るための、心のバンドエイド
子どもの心の健康の専門家、慶應義塾大学病院 小児科専門医 中村 俊一郎先生からのメッセージ
2024年1月1日、能登半島地震が起こりました。
胸を痛める映像・ニュースばかりです。
今も、余震と寒さの中、お子さんを守るために、多くの親御さんが高い緊張感の中、眠れぬ日々を過ごしていらっしゃるのではないかと想像します。
子どものメンタルヘルスに関わる小児科医として、子どもの心を守るために、親御さんのために、少しでも力になればという思いで【被災地の子どもと家族を守るための、心のバンドエイド】と題して、震災という危機的な状況で、どのようにお子さんと過ごすのが良いかをお伝えできればと思います。お子さんを持つ親御さんだけでなく、皆さんに読んでいただけたらと思います。
1.スキンシップを求めてくる子がいたら、“意識的に”応えてあげてください
不安を感じた子どもは、いつもよりも多くスキンシップを求めてくることがあります。震災という初めての体験で、自分が感じている不安をどう処理したらいいのか、どう言葉にしたらいいのか分からないからこそ、子どもはスキンシップを求めます。全てが変わった震災の中で、“変わらないお母さん・お父さんの感触”こそが安心の材料なのです。
避難所の慣れない生活の中で、お子さんの求めるスキンシップに応えることは親御さんにとっても大変なことだと思います。ただ、それでも、お子さんを守ることが、お子さんの安心につながり、お子さんの安心が明るい未来につながっていくはずです。加えて、親御さんにとっても、お子さんとのスキンシップは重要です。不安の中で、大切な我が子の感触を確かめられることが、親御さんの安心にもつながるからです。
2.気分をリフレッシュするために、運動したり、体を動かしましょう
運動や体を動かすこともストレス・不安の軽減につながります。体を動かすことで、ストレスホルモンが減り、幸福感をもたらすエンドルフィンというホルモンが増えるのです。避難場所では体を動かすことは難しいかもしれませんが、親御さん、大人の方々には子どもが体を動かすことの重要性を理解し、許してあげてほしいですし、ぜひ一緒に体を動かしてほしいと思います。
3.「もし、また地震が来たらどうするか」、親子で話し合っておきましょう
災害が起きた時、不安だからこそ、怖かったからこそ、お子さんたちが繰り返し地震の話をしたり、また起こるかも…と話しかけてくることがあるかもしれません。お子さんの言葉は否定せず耳を傾け「怖かったよね」「心配だよね」と、声をかけてあげてください。
その上で「もしまた地震が起こったら、〇〇に避難しようね」など、 現実的な計画を話し合ってください。お母さん・お父さんと事前に準備ができることで、もし次に地震が起こった時にも、「お母さん・お父さんと決めた通りに動こう」とお子さん自身が考えることができ、お子さんの不安を減らせます。
避難する中で、また地震の話をすることはとても苦しいことだと思います。そして、少しでもお子さんたちを安心させたいからこそ、「絶対起こらないよ」と伝えたくなると思います。しかし、地震が絶対起こらない、といった表現は現実的ではなく、使わないほうが良いと言われています。お子さんが「地震の話はしてはいけないんだ」と理解して、不安を一人で抱えてしまうからです。
事前にお母さん・お父さんと話し合えていることで、子ども自身が「対処できる」という実感を持ち、「何か起こっても、家族や大人がついていてくれるから安心」と思える感覚につながり、子ども達の安心感が守られます。
4.子どもが「生活の見通し」を持てるような援助をしましょう
混乱した災害時の中では特に「今日1日の生活に見通しを持てること」が精神的に安定するために重要な手掛かりになります。今日やること・今日の食事の予定・掃除をするタイミング・起きる時間・寝る時間、どんな些細なことでも良いので、子どもが見通しを持てるように意識的に予定を伝えてあげてください。
震災・避難時の初期段階においては、誰しも予定の見通しが立たない状況におかれると思います。そんな時でも、ほんの短期間の、少し先のことでもわかることがあれば、それだけで子どもにとっては「見通し」になります。見通しがつけば、自分なりに工夫して、災害時の生活に自ら適応することにも繋がります。
5.「あなたのせいではない」と伝えてあげてください
子どもは、困っている親御さん・家族を見て、“悲惨な出来事を自分のせいだ”と考えてしまう場合があります。その後ろめたさから、落ち込んだり話せなくなってしまうことがあるのです。もし、お子さんが「僕のせい?」「私のせい?」と考えていたら、バカにせず、目を見て「あなたのせいではないよ」と何度も何度も伝えてあげてください。お母さん・お父さんとのやりとりで子どもは安心していきます。
6.つらい記憶を呼び起こす物事からお子さんを守ってください
大人が気がつかないうちに、子どもがつらい出来事・恐怖を感じるような映像に長く曝されてしまっている場合があります。意識的にテレビやスマホなどとの接触時間を減らしましょう。
7.親御さん自身も、自分の体やこころの変化に気がつけるようにし、ストレス対処に心がけましょう
最後は、親御さん自身に向けたメッセージです。親御さんはお子さんにとって、とても大切な存在です。そして当然ながら、お子さんだけでなく、親御さんもまた、支援の対象です。子どものケアに奔走し自分自身の問題を自覚しにくくなることも多いと思いますが、一度立ち止まって自分自身の体やこころの変化を見つめ、無理をしすぎないようにして欲しいです。
眠れない、イライラする、などのストレスの兆候が現れているときは、まずは自分の体の不調・心の不調・ストレスを感じている、という事実を認めることが大切です。誰かに自分の体験や気持ち、ストレスに感じていることを話してみましょう。ご家族間でお互いの気持ちを話したり、5分でも良いので交代で休息を取るのも、有効な解消法です。親御さんが少しでも休みを取れて、少しでもホッとできたら、きっとお子さん達も嬉しいはずです。
ぜひ、一息ついてほしいです。
まとめ
震災による困難な状況の中で、私たちにできることは、心を寄せ合い、目の前の、一つ一つの小さなケアを積み重ねていくことです。身体の安全を確保することから始め、日々の生活リズムを大切にし、身体を動かして心のバランスを取り戻しましょう。そして何よりも、家族がお互いに寄り添う時間を大切にしてください。親御さん自身の休息とケアも忘れないでください。
この記事が、心に疲れを抱えた被災地の皆さんにとって、心のバンドエイドになれば、と思います。震災の中でも、小さな思いやりが子どもたちを守り、明るい明日への一歩となるよう願っています。
参考文献:
自然災害などの影響を受けた子どもの心を支える5つのポイント:Save the Children
社会的養護における 災害時「子どもの心のケア」手引き

執筆・監修者プロフィール:
中村 俊一郎先生
慶應義塾大学医学部卒、同病院 小児科
小児科専門医・小児心身医学認定医・公認心理師・出生前コンサルト小児科医
普段は大学病院で病気のお子さん、病気を抱えるお子さんのきょうだい・親御さんのメンタルヘルスケアを担当。
<子どもの心の健康>から<日本の社会を変える>を合言葉に小児科医として活動中。