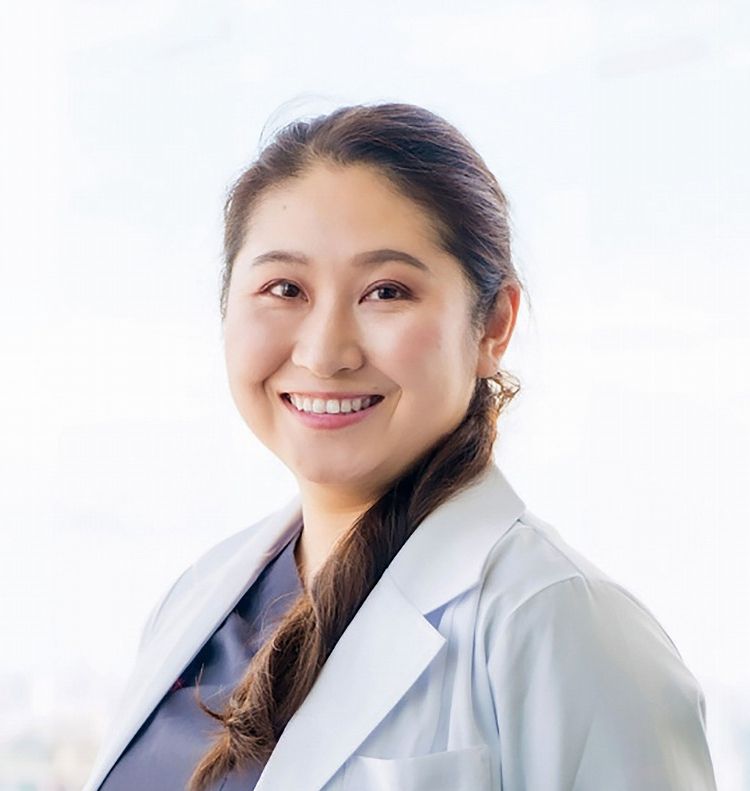子どものインフルエンザ:高熱はいつ下がる?症状の経過と対処法を小児科医が解説

お子さんが突然高熱を出すと、「もしかしてインフルエンザかも?」と心配になりますよね。特に熱が続くと、いつ下がるのか、受診のタイミングはいつかなど、不安が募るものです。この記事では、小児科医の視点から、インフルエンザの症状の経過や熱の下がり方、ご家庭でできるケア、そして医療機関にかかるべきサインについて、わかりやすく解説します
Contents
インフルエンザの基本知識と風邪との違い
インフルエンザは、毎年冬から春先にかけて流行するウイルス性の感染症で、子どもがかかると急な高熱や強い全身症状が現れやすいのが特徴です。一見すると風邪とよく似た症状もありますが、進行のスピードや症状の重さには大きな違いがあります。
特に乳幼児や小学生の子どもは免疫力がまだ発達途上であるため、感染しやすく、重症化することもあるため注意が必要です。風邪と混同して対応が遅れると、体調の悪化や合併症のリスクが高まることもあるため、正しい知識を持って見分けることが大切です。
インフルエンザウイルスの特徴と感染のしくみ
インフルエンザは、「インフルエンザウイルス」という特定のウイルスによって引き起こされます。大きく分けてA型、B型、C型の3種類がありますが、毎年の流行の中心となるのは主にA型とB型です。
これらのウイルスは、飛沫感染や接触感染を通じて広がります。
感染した人の咳やくしゃみの中にはウイルスが大量に含まれており、それを吸い込んだり、ウイルスが付着した手で目や口、鼻に触れたりすることで体内に入ります。子どもは手をよく口に運ぶことが多く、感染経路を自ら作りやすいため、家庭内でも広がりやすい傾向があります。
また、インフルエンザウイルスは非常に変異しやすく、毎年ウイルスの性質が少しずつ変化するため、毎年流行する型が異なり、そのたびに新たな免疫が必要になります。そのため、毎年のワクチン接種が予防として勧められていますが、予防接種を受けていても軽症で済むことがあるだけで、100%の予防効果があるわけではない点にも注意が必要です。
普通の風邪との違い:症状と進行の違い
インフルエンザと風邪は、どちらもウイルスによって起こる感染症ですが、その症状の強さや現れ方、経過のスピードには明確な違いがあります。
風邪は一般的に、のどの痛みや鼻水、くしゃみなどの局所的な症状から始まり、発熱しても微熱程度で済むことが多く、数日で自然に回復するのが特徴です。一方、インフルエンザは突然の高熱(38℃以上)や、頭痛、関節痛、倦怠感などの全身に及ぶ強い症状を伴って始まります。
また、風邪は発症の進み方がゆるやかであるのに対し、インフルエンザは発症から数時間で一気に症状が悪化することもあります。子どもの場合は、急な高熱にぐったりしてしまい、遊ばなくなったり、食事や水分が摂れなくなったりすることも少なくありません。
さらに、突然の高熱から始まり、呼吸器症状が後から目立ってくるケースがあるのもインフルエンザの特徴です。このような進行の違いを知っておくことで、保護者が早めに異変に気づき、適切な対応につなげることができます。
子どもがかかりやすい理由と家庭での注意点
子どもがインフルエンザにかかりやすいのは、体の中でウイルスに対抗するための免疫機能がまだ十分に発達していないからです。特に保育園や幼稚園、小学校などでは、子ども同士の距離が近く、咳やくしゃみを通してウイルスが広がりやすい環境が整っているため、感染リスクが高まります。
また、子どもは自分の体調の変化をうまく言葉にできないことも多く、親が気づかないうちに症状が進行している場合もあります。高熱が出ていても「暑い」「眠い」としか訴えない、または遊び続けてしまうこともあるため、体温や様子をこまめに観察することが大切です。
以下の表は、子どもが感染しやすい理由と、それに対する家庭での注意点をまとめたものです。
| 感染しやすい理由 | 家庭での注意点 |
|---|---|
| 免疫力が未発達 | 日ごろからバランスの取れた食事と十分な睡眠を心がける |
| 手洗いや咳エチケットが不十分 | 帰宅後の手洗いやうがいを習慣にするよう声かけする |
| 集団生活で接触機会が多い | 流行期は人混みを避け、必要があれば登園・登校を控える |
| 症状に気づきにくい・うまく伝えられない | ぐったりしていないか、顔色や食欲、水分摂取量を注意深く見る |
こうした背景から、保護者がインフルエンザの典型的な症状や経過を理解しておくことが、早期の対応につながります。また、本人だけでなく、家族全体の予防意識を高めることも感染拡大を防ぐうえでとても重要です。
発熱の経過と高熱が続く場合の考え方
子どもがインフルエンザにかかると、最も保護者が不安を感じやすいのが「熱がいつまで続くのか」という点です。特に高熱が続くと、体力の消耗や脱水の心配も出てくるため、症状の典型的な経過をあらかじめ知っておくことが大切です。
熱の下がり方には個人差がありますが、通常は数日以内に解熱へ向かうケースが多く見られます。ただし、途中で再び熱が上がることもあるため、慎重な見守りが必要です。ここでは、発熱の経過とその捉え方について詳しく見ていきましょう。
発症から何日で熱が下がる?典型的な経過とは
インフルエンザにかかった子どもは、発症からすぐに38℃以上の高熱を出すことが多く、その熱は通常、3〜5日目頃までに下がってくるとされています。このタイミングは、インフルエンザウイルスが体内で活発に増殖する期間を過ぎ、免疫がウイルスを排除し始める時期にあたります。
以下に、一般的な発熱の経過を日数ごとにまとめます。
| 日数の目安 | 状態と症状の特徴 |
|---|---|
| 0〜1日目 | 突然の高熱(38℃以上)と全身症状(頭痛・関節痛・だるさ)で始まる |
| 2〜3日目 | 高熱が続くが、症状がピークに近づく |
| 3〜5日目 | 解熱に向かうことが多い。ただし、個人差あり |
| 5日目以降 | 咳や鼻水などの呼吸器症状が目立つ時期。全体的に回復傾向へ |
ただし、これはあくまで目安であり、ワクチン接種の有無や体質、感染したウイルスの型によっても経過は異なります。
また、インフルエンザ治療薬(抗ウイルス薬)を使用している場合は、もう少し早く熱が下がることもありますが、それでも症状が完全に消えるには時間がかかることもあります。
熱が下がったからといってすぐに安心せず、体力回復を最優先にした生活を心がけることが大切です。
二峰性発熱や長引く高熱に要注意
インフルエンザの発熱は、多くの場合3〜5日で落ち着く傾向がありますが、なかにはいったん熱が下がったあと、半日から1日程度で再び高熱が出ることがあります。
これはウイルスの影響が体にまだ残っていることが原因と考えられており、必ずしも重症化を意味するわけではありませんが、保護者にとっては非常に不安な症状です。
特に、最初に熱が下がったことで安心して登園・登校を再開した後に再び発熱した場合、周囲への感染のリスクもあるため、慎重な判断が求められます。また、再発熱後もぐったりしている、食事や水分が取れない、顔色が悪いなどの変化がある場合は、二次感染や合併症の可能性も視野に入れる必要があります。
一方で、発熱が5日以上続く、または熱が下がる兆しがまったく見えないときも注意が必要です。このようなケースでは、インフルエンザ単独ではなく、気管支炎や肺炎、中耳炎などの合併症が起きている可能性があるため、早めに小児科での診察を受けることがすすめられます。
以下は、特に注意したい高熱のパターンと対応の目安です。
| 高熱のパターン | 対応の目安 |
|---|---|
| 一度下がった熱が再び38℃以上に上昇 | 症状が軽ければ様子を見てよい場合もあり |
| 発熱が5日以上続く | 合併症のリスク。小児科への受診を検討 |
| 解熱後も咳や呼吸が苦しそう | 呼吸器系合併症の疑いあり。医療機関への相談を |
保護者が「いつ受診すべきか」の判断に迷うこともあるかもしれませんが、長引く熱や再発熱は、決して様子見だけで済ませず、少しでも異変を感じたら医師に相談するのが安心です。
38度以上の熱が続く場合に考えられる原因
インフルエンザでは高熱が特徴のひとつですが、38度以上の熱が5日以上続く場合や、一度下がった熱が再び上がって下がらない場合には、単なるウイルスの影響だけでなく、他の要因が関わっている可能性も考えなければなりません。
もっとも代表的なのが、合併症の存在です。子どもの場合、インフルエンザに伴って起こりやすい合併症には次のようなものがあります。
- 気管支炎・肺炎:咳が激しくなり、呼吸が苦しそうになる。ゼーゼーという音がすることも。
- 中耳炎:熱が下がらず、さらに耳を触って痛がる、機嫌が悪いといったサインが見られる。
- インフルエンザ脳症(まれだが重篤):けいれんや意味不明な言動、反応が鈍いなど。
また、水分不足による脱水症状や、体力の消耗による回復の遅れなども、熱が長引く原因となることがあります。特に乳幼児は体内の水分量が少なく、発熱によってすぐに脱水状態に陥りやすいため、「熱が高いこと」そのものよりも、熱によって体がどのような影響を受けているかをしっかり見ていくことが大切です。
以下のような状態が見られる場合は、速やかに医療機関を受診することがすすめられます。
- 5日以上38℃以上の熱が続いている
- 再び高熱になり、下がる気配がない
- 咳や呼吸の異常(呼吸が速い・苦しそう)
- 顔色が青白い、ぼんやりしている、反応がにぶい
- 水分がとれず尿の回数が少ない
こうした症状は、「病気が長引いている」というより、「症状が進んでしまっている」サインであることが多く、早めの対応が回復を早めるカギとなります。子どもの様子がいつもと違うと感じたら、遠慮せず受診を検討しましょう。
症状別のホームケア:家庭でできる対応
インフルエンザの治療において最も大切なのは、安静と家庭での適切なケアです。医師から薬が処方されることもありますが、それだけに頼るのではなく、子どもが無理なく回復できるような環境づくりや、こまやかなサポートが何よりも重要です。
特に発熱や食欲不振があるときは、水分や栄養の取り方に注意を払いながら、子どもの様子をよく観察することが求められます。ここでは、家庭で行える具体的なケアについて、症状別に見ていきましょう。
水分補給と食事の工夫:脱水と体力低下を防ぐ
高熱が続くと、体は汗をかきやすくなるだけでなく、呼吸も速くなり、知らないうちに体内の水分が失われていきます。子どもは大人に比べて体が小さい分、脱水になりやすいため、こまめな水分補給がとても大切です。
ただし、熱やだるさで飲んだり食べたりするのがつらいときもあるため、無理に大量に与えようとせず、少量ずつを繰り返すようにしましょう。以下は、子どもがインフルエンザのときにおすすめの水分や食事の例です。
| 状態 | おすすめの水分・食事 |
|---|---|
| 発熱中 | 経口補水液(OS-1など)、麦茶、白湯、スープなど |
| 食欲不振時 | おかゆ、うどん、ゼリー、プリン、アイスクリームなど |
特に経口補水液は、水分と一緒に電解質(ナトリウムなど)も補えるため、脱水が心配なときに有効です。ただし、味に抵抗があるお子さんもいるため、飲み慣れたものから少しずつ与えるのが良いでしょう。
また、食事についても、「食べさせなければ」と焦らず、本人が欲しがるタイミングに合わせて、消化のよいものを中心に少しずつ用意していきましょう。無理に食べさせようとすると、吐いてしまったり、かえって体力を消耗してしまうこともあります。
水分が摂れていて、おしっこが出ているなら、多少食事の量が減っていても、すぐに栄養失調になることはないので心配しすぎなくて大丈夫です。回復とともに、徐々に食欲も戻ってきます。
安静と睡眠:体力回復のための環境づくり
インフルエンザの回復には、薬よりも体をしっかり休めることが大切です。特に子どもは、ウイルスと戦う過程で多くのエネルギーを消耗するため、静かで安心できる環境のなかで、十分な睡眠と安静を確保することが、体力の回復を助けるポイントになります。
高熱が出ているときや全身がだるいときは、無理に動かそうとせず、横になって休ませてあげることが最優先です。お昼寝の時間にこだわらず、眠たそうにしているときはこまめに寝かせてあげることで、体力の消耗を抑えられます。
また、室内環境を整えることも回復をサポートする要素のひとつです。以下のような点に気を配ってみましょう。
| 環境の工夫 | ポイント |
|---|---|
| 室温・湿度の調整 | 室温は20〜22℃程度、湿度は50〜60%を目安に保つ |
| 音や光の刺激を抑える | 照明を少し落とし、テレビや動画の音量を控えめに |
| 寝具やパジャマの通気性 | 汗をかいたらすぐに着替えさせ、清潔で快適な状態を保つ |
| 看病する側の接し方 | 不安を和らげるようにやさしく声をかけ、そばで見守る |
また、「眠っていないと治らないのでは」と焦る必要はありません。子どもは不調を感じると自然と体を休める行動をとりますので、たとえ起きていても静かに絵本を読んだり、横になっているだけでも体力の温存につながります。
大切なのは、「何もしない時間」を意識的に作ってあげること。遊びたがっても無理をさせず、ゆっくりと体が治ろうとする力を支える姿勢が、家庭でできる最大のサポートになります。
解熱剤の使い方と注意点:医師の指示を守る
インフルエンザによる高熱は、見ている側にとってもとても心配ですが、熱が出ること自体は、体がウイルスと戦っている証拠でもあります。そのため、必ずしもすぐに熱を下げなければいけないというわけではありません。
ただし、熱が原因で子どもがつらそうにしていたり、水分がとれずぐったりしているときは、解熱剤を使うことで体の負担を軽くしてあげることができます。使いどきの目安としては、以下のような状況が挙げられます。
- 熱が高くて眠れない
- 水分をとれず、ぐったりしている
- 強い頭痛や関節痛があると訴える
これらに当てはまる場合には、医師から処方された解熱剤を決められた用量と間隔を守って使うようにしましょう。
市販の解熱剤を使いたくなる場合もあるかもしれませんが、インフルエンザのときに避けるべき成分(たとえばアスピリンなど)もあるため、自己判断での使用は控えるべきです。
特に15歳未満の子どもには、インフルエンザ脳症やライ症候群といった重篤な副作用を引き起こすおそれがあるため、小児科で処方された薬以外は原則として使わないことが望まれます。
また、解熱剤はあくまで一時的に熱を下げるためのものであり、病気そのものを治す薬ではありません。熱が下がったからといってすぐに活動を再開すると、体力が回復しきっていないために、かえって症状がぶり返すこともあります。解熱後もしばらくは安静に過ごすことが大切です。
最後に、薬の効果や副作用に不安があるときは、医師や薬剤師に相談することが何よりも確実です。ネットやSNSの情報に惑わされず、お子さんの状態に合ったケアを選ぶことが、安心につながります。
[CTA]
受診の目安と医療機関にかかるタイミング
子どもが高熱を出していると、「このまま様子を見ていいのか」「すぐ病院へ連れて行くべきか」と迷うことがあるかもしれません。
インフルエンザは自然に回復することも多い一方で、症状が重くなっているサインを見逃さず、適切なタイミングで受診することが大切です。特に乳幼児は体力が少なく、症状の進行が早いこともあるため、「少しおかしいかも」と感じたときに、早めに医師へ相談できるよう備えておくことが重要です。
ここからは、受診の判断材料となる症状や、医療機関にかかるべき具体的なタイミングについて解説していきます。
医療機関に行くべき症状とタイミング
インフルエンザは数日で熱が下がり、自然に回復するケースが多いとはいえ、以下のような症状が見られた場合は、早めの受診が必要です。
- 38度以上の高熱が5日以上続いている
- 熱がいったん下がったあと、再び高熱が出て下がらない
- 顔色が悪く、呼吸が苦しそう、呼吸の回数が多い
- 水分がほとんどとれず、おしっこの回数が明らかに少ない
- 呼びかけに反応しない、反応が鈍い、意識がはっきりしない
- けいれんを起こした
こうした症状は、インフルエンザによる合併症(肺炎、中耳炎、インフルエンザ脳症など)や脱水、発熱けいれんなどの可能性があるため、「もう少し様子を見ようかな」と迷うより、すぐに医師の診察を受けるほうが安心です。
特に夜間や休日など、すぐに受診できない時間帯に体調が悪化した場合でも、オンライン診療を活用すれば、自宅にいながら小児科医に相談することができます。不安を一人で抱え込まず、医療の力をうまく使うことが、子どもの命と健康を守ることにつながります。
また、すでにインフルエンザと診断されている場合でも、回復が遅れている、咳がひどくなってきた、熱がぶり返してきたなどの変化があったときは、再受診をためらわず、「今の状態を伝えて、必要な処置を受ける」という意識が大切です。
緊急性の高い症状:けいれん・意識障害・呼吸困難
インフルエンザにかかったお子さんの症状が、いつもと明らかに違うと感じたとき――それは、ためらわずに医療機関へ連絡すべきタイミングかもしれません。なかでも、けいれん、意識の変化、呼吸の異常といった症状は、緊急性が高く、早急な対応が必要です。
まず注意したいのが、「熱性けいれん」です。生後6か月〜5歳ごろまでの子どもに多く、急な高熱に反応して一時的にけいれんを起こすことがあります。手足がピクピクと震える、目線が合わない、体が突っ張るといった様子が見られた場合は、すぐに横向きに寝かせ、口の中に物を入れず、時間を測りながら様子を見ることが基本です。
ただし、以下のような状態があれば、迷わず救急要請またはすぐに病院を受診する必要があります。
- けいれんが 5分以上 続いている
- けいれん後も 意識が戻らない、反応がない
- 意味不明なことを話す、視線が合わないなどの 意識障害がある
- 呼吸が苦しそう、浅く速い呼吸をしている
- 唇が紫がかっている、顔色が非常に悪い
- 呼びかけに反応しない、ぐったりして動かない
これらは、インフルエンザ脳症や重度の脱水、肺炎、低酸素状態などの重大な疾患のサインである可能性があるため、すぐに医師の診察を受ける必要があります。
また、こうした緊急事態は突然起こることが多く、慌てずに対応できるよう、日頃から「どこに相談するか」「何を準備しておくか」を家族で話し合っておくと安心です。小児救急電話相談(#8000)など、地域の相談窓口を把握しておくことも、いざというときの助けになります。
インフルエンザ検査と治療法の基礎知識
お子さんがインフルエンザのような症状を示したとき、病院での診察に加えて行われることが多いのが「インフルエンザ検査」です。迅速検査キットと呼ばれる方法が一般的で、鼻の奥からぬぐった粘液を使ってウイルスの有無を調べるものです。
検査自体は数分で結果が出ますが、発熱後すぐの段階ではウイルス量が少なく、正確な結果が出にくいこともあります。そのため、多くの小児科では発熱から12時間程度が経過してからの検査を推奨することがあります。
すでにご家庭でインフルエンザが流行している場合などは、症状から判断して検査を省略することもあり得ます。治療においては、必要に応じて抗インフルエンザ薬(抗ウイルス薬)が処方されることがあります。代表的な薬には以下のような種類があります。
| 薬の名前(一般名) | 服用方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| オセルタミビル | 内服(5日間) | 最も広く使われている内服薬 |
| ザナミビル | 吸入(5日間) | 吸入式のため吸うのが難しい子も |
| ラニナミビル | 吸入(1回) | 1回の吸入で治療が完了するタイプ |
| バロキサビル | 内服(1回) | 比較的新しい。耐性の問題が指摘されることも |
ただし、抗ウイルス薬は万能ではありません。使うことで症状のピークを半日ほど短くする可能性はありますが、症状が軽く済むとは限らず、副作用にも注意が必要です。すべての子どもに必ず処方されるわけではなく、年齢や症状、持病の有無などを考慮して医師が判断します。
また、抗生物質との混同も多いですが、インフルエンザはウイルスによる病気のため、抗生物質は効きません。これは「風邪薬」として処方されることのある薬についても同様で、あくまで咳や鼻水など症状を和らげるための対症療法であることを理解しておくと、薬への期待や不安を正しくコントロールできます。
治療は、薬に頼るだけでなく、安静、栄養、水分補給といった日々のケアが軸になります。医師の指示に従いながら、焦らずじっくりとお子さんの回復を見守っていきましょう。
回復期の過ごし方と再登園・再登校の目安
インフルエンザの発熱が治まり始めると、保護者としては「もう大丈夫かな?」「いつから保育園・学校に行けるのかな?」と考えるようになります。ただし、熱が下がっても、すぐに元通りの生活に戻れるわけではありません。
子どもの体は、ウイルスとの闘いでかなりのエネルギーを使っているため、回復期にも注意深く体調を観察し、無理のない生活リズムに戻していくことが大切です。このセクションでは、回復期に見られやすい症状や、体調管理のポイントを詳しくご紹介します。
回復期に見られる症状と体調管理のポイント
インフルエンザの発熱が落ち着いてきた後も、子どもによっては次のような軽度の症状がしばらく続くことがあります。
- だるさ(倦怠感)
- 咳や鼻水
- 食欲の低下
- 眠気や集中力の低下
これらは、ウイルスによる影響がまだ完全には抜けきっていないことや、体力が落ちているために起こるもので、決して珍しいことではありません。
そのため、「熱が下がった=全快」と考えず、本人の体調や様子を見ながら、徐々に日常に戻していくことが大切です。以下のような体調管理のポイントを意識してみましょう。
| 管理ポイント | 内容 |
|---|---|
| 睡眠をしっかり取る | 体力回復に睡眠は不可欠。昼寝を嫌がらなければ無理せず休ませる |
| 食事は無理をさせない | 食欲が戻ってきたら、消化の良いものから少しずつ再開。食べたがる量でOK |
| 水分を継続して摂る | 熱が下がっても脱水状態が続くことがある。引き続きこまめに水分補給を |
| 活動量を調整する | 完全に元気になるまでは外遊びや登園・登校を急がず、家で静かに過ごす時間を多めに |
また、「回復したと思ったら、また熱が出た」「咳がひどくなっている」といった症状のぶり返しが見られた場合には、合併症の可能性もあるため、再度小児科を受診するのが安心です。
保護者としては、早く通常の生活に戻したい気持ちもあるかと思いますが、焦らず、一歩ずつ回復をサポートする姿勢が、結果的にお子さんの健康回復を早めることにもつながります。
再発リスクを防ぐために注意したい生活習慣
インフルエンザは一度かかればそれで終わり、というわけではありません。流行期のあいだは、回復した後でも再び感染するリスクがゼロではないため、回復後も引き続き予防を意識した生活を送ることが大切です。
とくに、回復してすぐに無理をしてしまうと、体力が十分に戻っていない状態で他のウイルスや細菌に感染してしまうこともあります。そうなると、症状がぶり返すだけでなく、気管支炎や中耳炎などの合併症につながるリスクもあります。
以下は、再発や二次感染を防ぐために、回復期に意識したい生活習慣です。
- 手洗い・うがいの継続
症状が落ち着いても、ウイルスは身の回りに存在しています。登園・登校前や帰宅後の手洗いを習慣づけましょう。 - マスクの着用(必要に応じて)
特に流行のピーク時期には、人混みに出る際や、まだ咳が残っているときはマスクの着用を続けるのも一つの方法です。 - バランスの良い食事と十分な睡眠
体力を回復し免疫力を高めるために、ビタミンやタンパク質を含む食事を意識しつつ、夜は早めの就寝を心がけましょう。 - 活動の再開は少しずつ
完全に元気そうに見えても、体の中はまだ本調子ではないことがあります。登園・登校の再開後も、無理のないスケジュールで生活を整えていきましょう。
また、家族のなかにまだ発症していない人がいる場合、家庭内での感染対策も引き続き重要です。食事の共有やタオルの共用は避け、定期的な換気や加湿など、基本的な予防策を徹底しましょう。
一度回復したあとも、「もう大丈夫」と油断せず、数日間は様子を見るつもりで、少しゆっくり目のペースで過ごすことが、お子さんの体と心の回復を支えることにつながります。
登園・登校の再開はいつから?医師の診断書は必要?
お子さんの体調が落ち着いてくると、「そろそろ登園(登校)させてもいいのかな?」と考えるご家庭も多いと思います。ただし、インフルエンザは発熱が治まってもウイルスがしばらく体内に残っているため、周囲への感染を防ぐための登園・登校の基準が法律で定められています。
■ 登園・登校の再開目安(学校保健安全法)
学校保健安全法によると、インフルエンザにかかった場合の出席停止期間は以下のとおりです。
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」
これは、ウイルスの排出が最も多い時期を過ぎてから集団生活に戻るようにするための基準です。
例えば、1月10日に発症し、1月12日に解熱した場合:
- 発症日:1月10日(0日目)
- 5日経過:1月15日
- 解熱後2日経過:1月14日(幼児は1月15日)
したがって、1月15日以降に登園・登校が可能となります(医師の判断があればそれに従います)。
■ 医師の診断書(治癒証明書)は必要?
登園・登校にあたり、医師の「治癒証明書」や「登園許可証」が必要かどうかは、園や学校、地域によって異なります。
- 保護者の署名による「登園届」でOK
- 医師の診断書の提出が必要
- 医療機関での診断書発行(自費)を求められることもあり
などの対応がありますので、事前に所属園・学校の方針を確認しておくと安心です。
また、登園・登校を再開する際は、咳や鼻水などの残る症状が強くないか、体力が十分に戻っているかも大切な確認ポイントです。体調が安定していることを最優先にし、焦らずゆっくり復帰を進めていきましょう。
よくある質問
Q子どものインフルエンザは、何日くらいで熱が下がるのが一般的ですか?
A多くの場合、発症から3〜5日ほどで解熱に向かうことが多いですが、個人差があります。回復が遅いときや、いったん下がった熱が再び上がる「二峰性発熱」が見られるときは、医師への相談が安心です。
Q熱が下がったのに咳や鼻水が続いています。登園しても大丈夫?
A熱が下がっても体力が回復しきっていない場合は、無理に登園・登校を再開すると再発リスクが高まります。咳や全身のだるさが残っているようであれば、数日ゆっくり休ませることをおすすめします。
Qインフルエンザと風邪の違いは、具体的にどう見分ければいいですか?
A風邪は徐々に症状が出てくることが多いのに対し、インフルエンザは突然38℃以上の高熱が出ることが特徴です。全身の痛みや倦怠感が強く、短時間で悪化するのも見分けるポイントです。
Q受診のタイミングがわかりません。どういう症状のときに病院へ行くべきですか?
A以下のようなときは、すぐに受診を検討してください: ・5日以上高熱が続く ・再度高熱が出た ・呼吸が苦しい、顔色が悪い ・けいれんや意識がもうろうとする 判断に迷うときは、小児科やオンライン診療で相談すると安心です。
Q子どもがインフルエンザになった場合、家族への感染を防ぐにはどうすればいいですか?
A家庭内感染を防ぐには、以下の対策が効果的です: ・手洗い・うがいの徹底 ・共有物(タオルや食器)の分離 ・部屋の換気と加湿 ・看病する保護者もマスクを着用 特に兄弟がいる場合は、遊びの距離を少し保つ意識も大切です。
まとめ:焦らず安心して見守るために
子どものインフルエンザは、突然の高熱や強い全身症状など、親にとっては心配が尽きない病気です。しかし、症状の典型的な経過や対処法、受診の目安をあらかじめ知っておくことで、必要以上に慌てず、落ち着いて対応することができます。
高熱がいつまで続くのか、解熱剤はどう使えばよいのか、再登園のタイミングはいつか――一つひとつの疑問に丁寧に向き合いながら、お子さんの体調を見守っていくことが、安心と回復につながる第一歩です。
そして、夜間や休日など、すぐに受診できないタイミングで不安を感じたときは、医療につながる手段をあらかじめ準備しておくことも大切です。
そんな時に頼りになるのがオンライン診療アプリ「みてねコールドクター」です。
- 24時間365日、最短5分で医師の診察を受けられる
- 薬は近隣の薬局で受け取れるほか、全国配送(北海道、沖縄県、離島を除く)、一部地域では即日配送にも対応
- 登園・登校に必要な診断書や登園許可証の発行が可能
- システム利用料は無料で、健康保険や子どもの医療費助成制度にも対応
「みてねコールドクター」のアプリをインストールすれば、保護者の不安を軽減しながら、お子さんの健康を安心してサポートできます。あらかじめご家族の情報を登録しておけば、いざという時にスムーズにご利用いただけます。
家族のお守りに、みてねコールドクターをぜひご活用ください。
公式サイトはこちら:https://calldoctor.jp/
[CTA]