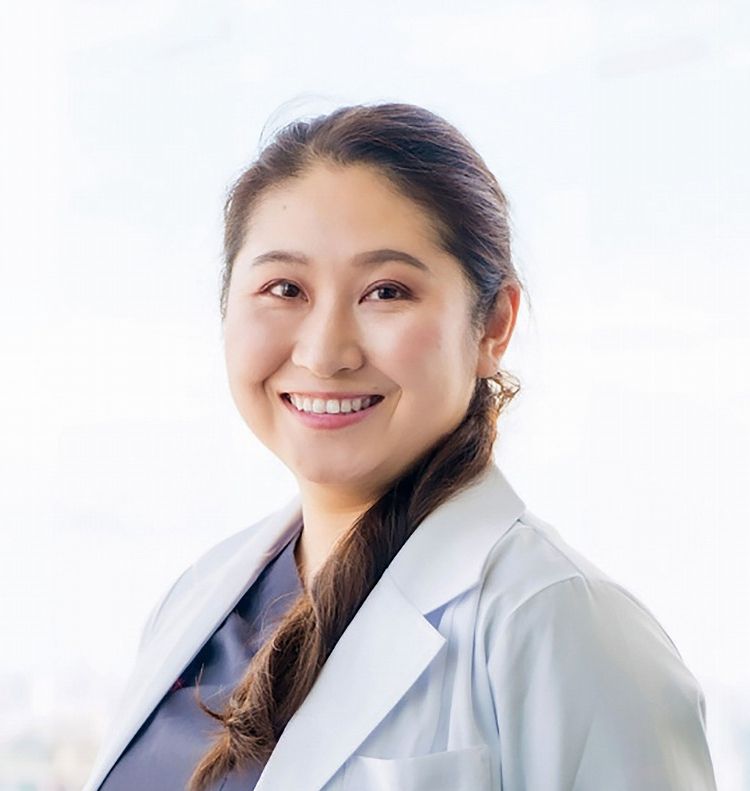子どもの咳が止まらないとき|夜に出やすい原因と対処法を小児科医が解説

夜になると急に咳が強くなり、何度も起きてしまう——保護者にとってとても心配な場面です。実は、就寝時は副交感神経が優位になって気道が敏感になりやすいこと、鼻水が喉へ落ちること(後鼻漏)、乾燥や寝具のホコリといった刺激が重なり、咳が出やすくなります。背景には風邪だけでなく、アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎、気管支喘息、クループ、百日咳などの病気が潜むこともあります。この記事では、夜間に咳が悪化する原因をやさしく整理し、家庭でできる対処法(上半身を高くする、加湿、水分補給、鼻水吸引、1歳以上でははちみつの活用など)を具体的に解説。さらに、受診の目安や夜間・休日の相談先まで、小児科医の視点でわかりやすくお伝えします。焦らず、できることから整えていきましょう。
Contents
夜に咳が悪化する理由を知ろう
夜になるとお子さんの咳が強くなるのは、多くの家庭で見られる自然な現象です。日中は落ち着いていても、寝かしつけの時間になると「コンコン」と咳が出て眠れなくなることがあります。これは単に風邪が悪化しているわけではなく、体のリズムや環境の変化が関係しています。
自律神経の影響で夜は体がリラックスモードに切り替わり、で気道が狭くなりやすくなります。また、寝ている姿勢では鼻水が喉に流れ込み(後鼻漏)、それが刺激となって咳を誘発します。さらに、暖房による乾燥した空気や、寝具にたまったホコリ・ダニなどのアレルゲンも咳を悪化させる要因です。お子さんの咳が夜に強く出るのは、こうした複数の要素が重なるためであり、原因を知ることが適切な対処の第一歩になります。
自律神経の変化と夜間の咳
夜になると、活動を司る「交感神経」から、体を休める「副交感神経」へと切り替わります。この自律神経の変化により、気道の筋肉がゆるみやすくなる一方で、気道粘膜の血流が増えて腫れやすくなります。その結果、咳受容体が刺激を受けやすくなり、軽い炎症や痰でも強い咳が出るようになります。特に気管支喘息のあるお子さんでは、この夜間の自律神経変化が症状悪化の主な要因となることがあります。
鼻水が喉に落ちる「後鼻漏」が原因のことも
風邪やアレルギー性鼻炎があると、鼻水が喉の奥に流れ込む「後鼻漏(こうびろう)」が起こります。寝ている姿勢では重力の影響で鼻水が喉の方にたまり、咳反射を引き起こします。この咳は夜間に目立つのが特徴で、朝方に「痰がからんだような咳」をすることもあります。寝る前に鼻吸い器で鼻水を取る、あるいは上半身を少し高くして寝かせるといった工夫が有効です。
空気の乾燥や寝具のホコリによる刺激
冬の暖房やエアコンの使用で、室内の湿度は40%以下になることがあります。乾燥した空気は喉や気管支を刺激し、咳を誘発します。また、寝具やカーペットに潜むハウスダストやダニも、気道のアレルギー反応を引き起こす要因になります。寝室の湿度を50〜60%に保つこと、週に1〜2回はシーツや枕カバーを洗濯し、布団を干すなど清潔を保つことが咳対策につながります。
アレルギーや喘息との関係
夜に咳が続く場合、単なる風邪ではなくアレルギー性咳嗽や気管支喘息が関係している可能性もあります。喘息は夜間や明け方に悪化することが多く、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」といった喘鳴(ぜんめい)を伴います。アレルギーが背景にある場合は、寝室のアレルゲン(ダニ、カビ、ペットの毛など)を減らす環境整備が大切です。もし夜間の咳が1週間以上続く、または毎晩のように強く出る場合は、かかりつけ小児科での相談をおすすめします。
咳が止まらないときに考えられる病気
夜間の咳が続く場合、単なる風邪と思っていても、実際にはさまざまな病気が関係していることがあります。咳の出方や音、続く期間、併発する症状によって原因を見分けることが大切です。多くの子どもの咳はウイルスによるものですが、長引いたり、特徴的な咳がある場合にはアレルギーや細菌感染、気道の炎症などが隠れていることもあります。ここでは、小児科でよく見られる主な原因疾患を整理してみましょう。
| 病名 | 主な特徴 | 咳の種類・期間 | 受診の目安 |
|---|---|---|---|
| 風邪(かぜ症候群) | 最も多い原因。ウイルス感染による気道の炎症。 | コンコンとした乾いた咳→痰が出る湿った咳に変化。1〜2週間で改善。 | 自然回復が多いが、長引く場合は受診を。 |
| 気管支喘息 | 夜間や明け方に悪化しやすい。アレルギー体質の子に多い。 | ヒューヒュー・ゼーゼーという音を伴う発作性の咳。 | 呼吸が苦しそう、発作が頻繁な場合は早めに受診。 |
| アレルギー性鼻炎・副鼻腔炎 | 鼻づまり・鼻水を伴う。 | 鼻水が喉に流れて刺激(後鼻漏)→長引く湿った咳。 | 鼻症状や長引く咳が続く場合に耳鼻科・小児科で相談。 |
| クループ症候群 | 声がかすれ、犬の鳴き声のような咳(ケンケン)。 | 急な発症。夜間に悪化しやすい。 | 息苦しさがある場合は救急受診を。 |
| 百日咳 | 咳が何週間も続く。息を吸うときに「ヒュー」という音。 | 長期間の連続的な咳(数週間〜数か月)。 | ワクチン未接種児や乳児では重症化リスクが高く要受診。 |
このように、咳の種類や伴う症状から、原因疾患をある程度推測することが可能です。ただし、自己判断で市販薬を使う前に、咳の性質や経過を観察し、必要に応じて小児科で診てもらうことが安心です。
風邪(かぜ症候群)による一時的な咳
最も一般的な原因であり、多くの子どもの咳は風邪によるものです。咳はウイルスや痰を外へ出す防御反応であり、すぐに止める必要はありません。通常は1〜2週間ほどで自然に治りますが、咳が長引く場合や発熱が3日以上続く場合は、別の感染症が潜んでいることがあります。家庭では水分補給と安静を心がけましょう。
気管支喘息とアレルギー性咳嗽
夜間や明け方に咳が強くなる場合は、気管支喘息の可能性があります。喘息は気道の慢性的な炎症によって、少しの刺激でも咳や喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)が出やすくなる病気です。発作が出たときは、吸入薬(β2刺激薬)やステロイド吸入で気道の炎症を抑える治療が行われます。
一方、アレルギー性咳嗽は喘鳴を伴わず、長期間にわたる乾いた咳が特徴です。ハウスダストや花粉などのアレルゲン除去と、抗アレルギー薬による治療が中心となります。
副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎による咳
長引く鼻水や鼻づまりを伴う場合、鼻水が喉に落ちる「後鼻漏」が咳の原因になることがあります。副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎では、寝ている間に鼻水が喉を刺激し、湿った咳が夜間に出やすくなります。家庭では鼻吸い器の活用や加湿を行い、改善しない場合は耳鼻科や小児科での診察が必要です。
クループ症候群・百日咳など注意すべき疾患
犬の鳴き声のような咳「ケンケン咳」が出る場合は、クループ症候群の可能性があります。喉の奥が腫れて呼吸が苦しくなるため、夜間に発作が出たら早めの受診が必要です。
また、百日咳は数週間から数か月も咳が続くことがあり、乳児の場合はヒューッという息継ぎ音(レプリーゼ)が特徴です。特に乳児では重症化しやすく、ワクチン接種を受けていない場合は注意が必要です。
夜の咳を和らげる家庭での対処法
お子さんが夜に咳き込み、なかなか眠れないとき、保護者も心配で寝つけなくなってしまいますね。けれど、家庭で少し工夫するだけで咳を軽くし、眠りを助けることができます。ここでは、薬に頼らずにできる自然なケアを中心に、小児科医の立場からやさしく解説します。夜の咳のケアの基本は、「呼吸を楽に」「喉を潤す」「刺激を減らす」の3つです。環境や姿勢、湿度を整えることで、咳の頻度を減らし、お子さんの安眠につなげましょう。
上半身を高くして呼吸を楽にする
咳で眠れないときに最も効果的なのが、上半身を少し高くして寝かせる姿勢です。背中や肩の下にクッションや折りたたんだタオルを入れ、頭から胸までをなだらかに傾けます。これにより気道が広がり、鼻水や痰が喉にたまりにくくなります。
また、気管支喘息や副鼻腔炎のあるお子さんにも、この姿勢は呼吸を助ける効果があります。赤ちゃんの場合は、ベビーベッドのマットレスの下にタオルを敷いて全体を5〜10度ほど傾けると安全です。寝かせた後は呼吸が苦しそうでないかを確認しましょう。
加湿・水分補給で喉の乾燥を防ぐ
乾燥した空気は、咳を悪化させる最大の要因の一つです。夜間は特に口呼吸になりやすく、喉や気道の粘膜が乾いて刺激に敏感になります。
理想的な湿度は50〜60%程度。加湿器を使うほか、濡れタオルを枕元に干す、洗濯物を室内にかけるなどの簡単な方法でも構いません。
また、寝る前に白湯や麦茶など温かい飲み物を少量与えると、喉の潤いを保てます。甘みのある飲み物やジュースは避け、刺激の少ないものを選びましょう。
はちみつ(1歳以上)の利用と注意点
1歳以上のお子さんには、ティースプーン1杯程度のはちみつが咳を和らげるのに有効です。はちみつの粘りが喉を保護し、保湿効果と自然な鎮静効果によって咳が落ち着きます。
ただし、1歳未満の赤ちゃんには絶対に与えてはいけません。これは「乳児ボツリヌス症」を引き起こすリスクがあるためです。
温かい飲み物に混ぜても良いですが、熱湯は避けて人肌程度のぬるま湯に溶かすようにしましょう。夜寝る前に与えると、喉の痛みや乾燥がやわらぎ、眠りやすくなります。
鼻水を吸って喉への刺激を減らす
咳の原因が鼻水にある場合、寝る前の鼻ケアがとても大切です。自分で鼻をかめない年齢のお子さんでは、鼻水が喉に流れ込み、咳を誘発してしまいます。
市販の鼻吸い器(電動・手動)を使って、無理のない範囲で鼻水を取り除いてあげましょう。特に寝る直前に行うことで、後鼻漏(鼻水が喉に落ちる現象)を防ぎ、夜間の咳を軽くできます。
また、鼻がつまっているときは温かい蒸しタオルで鼻の付け根を数分温めるのもおすすめです。血流が良くなり、鼻の通りが楽になります。
💡 ポイントまとめ表(家庭でできる夜の咳対策)
| 対処法 | 効果 | 補足 |
|---|---|---|
| 上半身を高くして寝かせる | 気道を広げ呼吸を楽に | クッションやタオルで調整 |
| 加湿(湿度50〜60%) | 喉と気道を保湿 | 濡れタオル・洗濯物も有効 |
| 温かい飲み物 | 喉を潤し咳をやわらげる | 白湯・麦茶など刺激の少ないもの |
| はちみつ(1歳以上) | 喉の炎症を鎮める | 絶対に1歳未満には与えない |
| 鼻水吸引 | 後鼻漏による咳を防ぐ | 就寝前に行うと効果的 |
咳止め薬や市販薬の使い方・注意点
お子さんの咳が長引くと、「薬で早く楽にしてあげたい」と思うのは当然のことです。ですが、子どもの咳は体の防御反応でもあり、無理に止めることが必ずしもよいとは限りません。薬を使うときは、咳の原因やお子さんの状態を見ながら、慎重に判断することが大切です。ここでは、家庭で気をつけておきたい薬の扱い方をわかりやすくまとめました。
市販の咳止め薬はいつ使うべき?
市販の咳止め薬は、大人と成分が似ていても、子どもには効き方や副作用が異なる場合があります。特に2歳未満の乳幼児では、咳止め成分が呼吸のリズムに影響することもあるため、自己判断での使用は避けましょう。
もし「咳で眠れない」「食事や水分が取れない」といったつらい症状がある場合は、医療機関でお子さんに合った薬を処方してもらうのが安心です。市販薬を選ぶときは、年齢に合った用量と使用期間を必ず確認し、添付の説明書をよく読みましょう。
小児用薬と大人用薬の違いを知る
大人が飲む薬を「少しだけ」と分けて与えるのは危険です。子どもの体は体重や代謝の仕組みが大人とは異なり、同じ成分でも過剰に作用してしまうことがあります。
子ども用の薬は、成分や配合量が細かく調整されています。飲みやすくするためにシロップや粉末になっているものも多く、味や香りにも工夫がされています。家庭では、保護者が正確な分量を計ること、飲み残しを保存しないことを徹底しましょう。
医師が処方する薬の種類と目的
病院で処方される咳の薬には、いくつかのタイプがあります。
- 去痰薬(きょたんやく):痰を柔らかくして出しやすくします。
- 鎮咳薬(ちんがいやく):咳の神経反射を和らげ、強い咳き込みを抑えます。
- 気管支拡張薬:気道を広げて呼吸を楽にします。喘息の発作時などに使われます。
- 抗ヒスタミン薬:鼻水やアレルギーによる咳に効果があります。
どの薬も、あくまで症状を和らげるための一時的なサポートです。服用後に眠気や食欲不振などが見られる場合は、使用を中止し医療機関へ相談しましょう。
薬に頼りすぎないケアの工夫
咳の多くは、薬だけで完全に止めることはできません。
それよりも、部屋を加湿して喉を潤す、水分をこまめに取る、安静に過ごすといった基本のケアを続けることが、回復への近道です。
また、咳が強くても元気で食欲がある場合は、体がウイルスとしっかり戦っている証拠です。焦らず見守りながら、必要に応じて受診を検討しましょう。
受診の目安と夜間・休日の対応
家庭でのケアを続けても咳が治まらないとき、「もう少し様子を見てもいいのかな?」「病院に行ったほうがいいのかな?」と迷うことがありますね。咳の多くは自然に治まりますが、なかには早めの受診が必要なケースもあります。ここでは、受診を検討すべきタイミングと、夜間や休日に利用できる相談先を紹介します。
早めに受診したほうがよい症状
風邪の咳でも、次のような様子が見られた場合は、早めに受診しましょう。
- 咳が1週間以上続いている
- 咳の勢いが強く、夜眠れない日が続いている
- 食欲が落ち、水分も取りにくい
- 38.5℃以上の熱が3日以上続く
- 耳を気にして触る(中耳炎を併発している可能性)
これらは「体の回復力では追いつかないサイン」のことがあります。小児科では、症状の背景に気管支炎・副鼻腔炎・アレルギー性咳嗽などがないかを確認し、必要に応じて吸入や薬の調整を行います。
緊急で医療機関を受診すべきサイン
次のような症状がある場合は、夜間や休日であっても救急外来や休日診療所を受診してください。
- 呼吸が苦しそう(肩で息をする、胸やお腹がペコペコへこむ)
- 「ヒューヒュー」「ゼーゼー」と音が聞こえる
- 顔色や唇の色が青白い、または紫色になっている
- 呼びかけに反応が鈍い、ぐったりしている
- 水分がまったく取れず、おしっこが半日以上出ていない
これらは気道の炎症が強くなっている状態で、早めの治療が必要です。特に、クループ症候群や喘息発作、重い肺炎などでは、夜間に急に症状が悪化することがあります。ためらわずに医療機関に相談してください。
夜間や休日に相談できる医療窓口
「受診するほどか分からないけれど心配」というときは、以下のような相談先を活用できます。
| 相談先 | 内容・利用時間 |
|---|---|
| #8000(こども医療でんわ相談) | 全国共通番号。小児科医や看護師が症状に応じた対応をアドバイス。夜間や休日も利用可能。 |
| 自治体の夜間・休日診療所 | 軽症でも受診できる医療機関。市区町村のホームページで確認できます。 |
| 救急安心センター(#7119) | 急な体調変化に対応。救急車を呼ぶべきか迷ったときに相談可能。 |
オンライン診療の活用方法(みてねコールドクター)
夜間や休日に「病院が開いていない」「移動が難しい」ときには、オンライン診療サービスを利用する方法もあります。
夜中に咳が強くなり、不安で眠れないときでも、スマートフォンから医師とつながれる安心感があります。家庭でのケアと医療をうまく組み合わせることで、お子さんの体調をやさしく支えられるでしょう。
よくある質問
Q夜になると咳がひどくなるのは、風邪が悪化しているということですか?
Aいいえ、必ずしも風邪が悪化しているわけではありません。夜は体がリラックスして副交感神経が優位になるため、気道が敏感になり咳が出やすくなります。さらに、寝る姿勢で鼻水が喉に流れる(後鼻漏)ことや、乾燥した空気も咳を悪化させる原因になります。
Q咳止めシロップを飲ませても大丈夫?
A市販の咳止め薬は、年齢や体重によって安全性が異なります。特に2歳未満の子どもには使用できない成分もあるため、自己判断で使うのは避けましょう。咳が強く眠れない場合や、水分が取れないほどつらそうなときは、医療機関でお子さんに合った薬を処方してもらうと安心です。
Q咳が長引くとき、どのくらいで病院へ行けばいいですか?
A多くの風邪による咳は1〜2週間程度で改善しますが、1週間以上続く、夜も眠れないほど強い咳、38.5℃以上の熱が3日以上続くといった場合は受診をおすすめします。また、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった音がする場合は、喘息や気管支炎などが関係している可能性があります。
Qはちみつをあげてもいいのは何歳からですか?
Aはちみつは1歳を過ぎてからであれば安全に使えます。喉の粘膜を保護し、咳をやわらげる効果がありますが、1歳未満の赤ちゃんには絶対に与えてはいけません。乳児ボツリヌス症という重い病気を引き起こすおそれがあります。与えるときは、ティースプーン1杯ほどをそのまま舐めさせるか、ぬるま湯に溶かして与えるとよいでしょう。
Q夜中に咳が止まらず眠れないとき、どうすればいいですか?
Aまずは上半身を少し高くして寝かせることで呼吸を楽にします。次に、加湿器を使って湿度を50〜60%に保ち、喉を潤すために少量の水分を与えましょう。もし咳が続いて息苦しそうなときや、顔色が悪い・唇が紫色などの症状がある場合は、夜間でも救急外来やオンライン診療に相談してください。
まとめ:焦らず、家庭でできるケアと早めの相談を
お子さんの咳は、見ている保護者にとってとても心配なものです。特に夜間に咳が強くなると、眠れないつらさと不安が重なりますね。けれど、ほとんどの場合は風邪などの一時的な症状であり、家庭での工夫によって楽になることが多いものです。
まずは、部屋の湿度を保ち(50〜60%)、上半身を少し高くして寝かせる、ぬるめの飲み物で喉を潤すといった基本のケアを続けましょう。1歳以上のお子さんなら少量のはちみつも喉の保護に役立ちます。鼻水が多いときは、寝る前に鼻吸い器で吸ってあげることで、夜間の咳を減らせます。
ただし、咳が長引いたり、息苦しさや高熱、顔色の悪さなどが見られる場合は、迷わず小児科を受診してください。お子さんの体調の変化に早く気づき、無理をさせずに休ませることが一番の回復への近道です。
そして、夜間や休日に不安を感じたときは、オンライン診療を利用するのも一つの手です。
そんな時に頼りになるのがオンライン診療アプリ「みてねコールドクター」です。
- 24時間365日、最短5分で医師の診察を受けられる
- 薬は近隣の薬局で受け取れるほか、全国配送(北海道、沖縄県、離島を除く)、一部地域では即日配送にも対応
- 登園・登校に必要な診断書や登園許可証の発行が可能
- システム利用料は無料で、健康保険や子どもの医療費助成制度にも対応
「みてねコールドクター」のアプリをインストールすれば、保護者の不安を軽減しながら、お子さんの健康を安心してサポートできます。あらかじめご家族の情報を登録しておけば、いざという時にスムーズにご利用いただけます。
家族のお守りに、みてねコールドクターをぜひご活用ください。
公式サイトはこちら:https://calldoctor.jp/
[CTA]