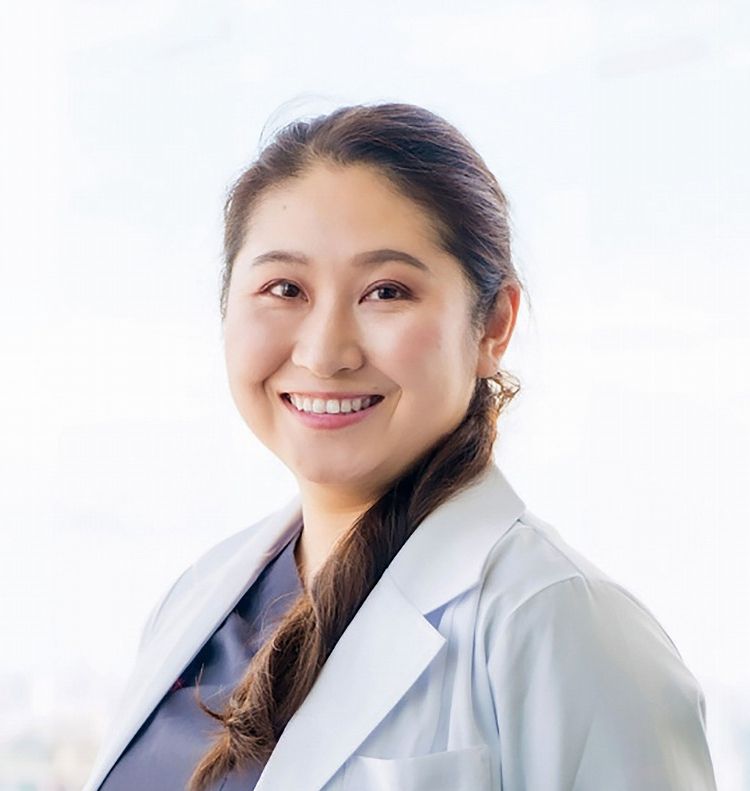子どもが新型コロナウイルス陽性になったら|自宅療養期間と登園・登校のタイミング

お子さんが「新型コロナウイルス陽性」とわかった瞬間、多くの保護者は不安で胸がいっぱいになるものです。発熱や咳などの症状があるときはもちろん、無症状であっても「いつまで自宅療養すればいいの?」「登園・登校の再開はいつ?」と、判断に迷うことが少なくありません。
本記事では、自宅療養の期間の考え方や、登園・登校の目安を中心に、家庭での過ごし方、感染対策のポイントをやさしく整理します。焦らず、正しい知識をもって対応できるように、学校保健安全法や厚生労働省の最新情報をもとに解説します。
Contents
子どもが新型コロナウイルス陽性になったときの基本対応
お子さんが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の検査で陽性になったとき、保護者は誰でも不安を感じるものです。まず大切なのは、落ち着いて状況を整理し、焦らずに対応することです。発症日や検査日を基準に自宅療養の期間を確認し、家庭内でできる感染対策を整えましょう。この章では、検査結果を受け取った直後に取るべき行動や、医療機関・学校との連絡の流れ、家庭での生活の整え方を順に紹介します。
検査で陽性になった直後にするべきこと
陽性とわかったら、まずは発症日や検査日を記録しておきましょう。これは、自宅療養期間を計算するうえでとても重要です。発熱や咳などの症状がある場合は、その症状が出た日が「発症日」となります。症状がない場合(無症状)は、検体を採取した日が基準です。
次に、勤務先や学校・保育園などに「陽性になったこと」「自宅療養に入ること」を連絡します。このとき、医療機関からの診断書や検査結果の報告が求められる場合もあるため、診療を受けたクリニックや検査センターの案内を確認しましょう。
また、家族の中に高齢者や基礎疾患のある方がいる場合は、同じ部屋で過ごさないなど早めの隔離対応を心がけます。
医師・学校・保健センターへの連絡のポイント
お子さんが通う保育園・幼稚園・学校には、登園や登校を控える必要があることを速やかに伝えましょう。多くの自治体では、保護者からの連絡とあわせて、医療機関の診断内容を学校側が確認する流れになっています。
医療機関への相談は、症状が軽い場合でも電話やオンライン診療で行うのが基本です。5日以上発熱が持続するときや、咳症状がが長引くとき、または水分が取れない場合は、病院で受診しましょう。夜間や休日は、地域の「子ども医療相談ダイヤル」や「みてねコールドクター」のようなオンライン診療サービスを活用すると安心です。
家庭での隔離や生活の準備
自宅療養に入るときは、できるだけ生活スペースを分けるようにします。お子さんが一人で過ごすのが難しい場合は、保護者が同室で見守りつつ、感染対策をしっかり行いましょう。お世話をする人は1人に決め、不織布マスクを着けて接することが基本です。
お子さんが過ごす部屋は、定期的に窓を開けて換気し、共有部分(ドアノブ・テーブル・トイレなど)はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムで拭き取ります。食器やタオルを共有しないようにし、使用後のティッシュやマスクは密閉した袋に入れて捨てましょう。
また、子どもが安心できるように、絵本やぬいぐるみなど心が落ち着くものをそばに置いてあげるのもよい工夫です。
家族が感染しないための初期対応
家庭内での感染を防ぐためには、「飛沫」「接触」「空気」の3つの経路を意識して遮断することが大切です。お世話をする人は必ずマスクを着け、できるだけ近距離での会話を控えます。子どもが使った食器や衣類は、通常の洗剤で洗えば十分ですが、乾燥機や日光でしっかり乾かすことを心がけてください。
トイレや洗面所など共用する場所は、使用後にアルコールで軽く拭く習慣をつけると効果的です。食事は同じテーブルでも距離を取るか、時間をずらして食べましょう。家族の誰かが発熱した場合は、すぐに検査を受け、家庭内での感染拡大を最小限に抑えるようにします。
自宅療養期間の考え方と登園・登校の目安
お子さんが新型コロナウイルス陽性と診断されたとき、最も気になるのが「いつまで自宅で療養すればよいのか」という点です。学校保健安全法では、新型コロナウイルス感染症はインフルエンザなどと同様に出席停止の対象と定められています。基本的な目安は、発症後5日を経過し、かつ症状が軽快してから1日を経過した時点(保育園・幼稚園の場合は2日を経過した時点)までが療養期間です。この章では、登園・登校のタイミングを具体例とともに解説し、家庭での判断をサポートします。
発症後5日を経過しかつ症状が軽快してから1日経過
厚生労働省と文部科学省の指針によると、登園・登校の再開は「発症後5日を経過し、かつ解熱してから1日を経過」したタイミングが基本となります。
発症日は0日目として数えるため、たとえば月曜日に発症した場合は、土曜日が5日目にあたります。もし木曜日に熱が下がり、咳も落ち着いた場合、金曜日が「症状軽快から1日経過」に該当し、土曜日以降に登園・登校が可能です。
ただし、症状が続く場合は焦らず、完全に回復してからの再開を心がけましょう。子どもによって回復のスピードには個人差があり、無理をすると症状が長引くこともあります。保護者は「少し元気になったからもう大丈夫」と思わず、1日ゆとりを持つくらいの判断が安心です。
再登園・再登校のタイミングの判断方法
再登園・再登校の判断は、「体調の回復」と「家庭内の感染状況」の両方を確認して決めるのが理想です。子ども本人の熱が下がっても、家族内で新たに陽性者が出ている場合は、もう数日様子を見るのが安心です。
登園再開の際は、園や学校に「発症日・解熱日・症状が落ち着いた日」を伝えるとスムーズです。
多くの施設では医師の診断書や登園許可証の提出を求めませんが、自治体によって対応が異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
登園後に注意したい行動と配慮のポイント
登園・登校を再開してから10日間は、ウイルスを排出する可能性がわずかに残るとされています。そのため、可能であれば不織布マスクの着用を続け、高齢者や基礎疾患を持つ方との接触を控えるのが望ましいとされています。
また、学校や園での活動に無理のないよう、体調の変化に気を配りましょう。発熱や強い咳が戻ってきた場合は、再度休養を取ることも大切です。保護者の「もう少し休ませよう」という判断が、長期的には子どもの回復を助けます。
家庭での過ごし方と感染対策の工夫
お子さんが自宅療養となった場合、保護者が最も気をつけたいのは「家庭内感染の拡大を防ぎながら、子どもの体調をしっかり回復させること」です。小さな子どもは自分で体調管理が難しく、保護者が寄り添いながら生活環境を整えることが何より大切です。この章では、家庭で実践できるケアと感染対策を、負担の少ない形でまとめました。
お子さんのケアで大切にしたい基本(安静・水分補給・食事)
療養中は「しっかり休む」「こまめに水分をとる」「無理のない食事をとる」――この3つが基本です。発熱がある間は無理に食べさせる必要はなく、水分補給を優先しましょう。麦茶や経口補水液、ぬるま湯など喉にやさしいものがおすすめです。
食事は、消化がよく栄養のあるものを少量ずつ与えるとよいでしょう。おかゆや野菜スープ、すりおろしりんごなど、喉を通りやすいものが適しています。また、熱や痛みがつらそうな場合は、医師に処方された解熱鎮痛剤(カロナールなど)を正しく使うことも回復の助けになります。
ケアのポイント(表)
| ケアのポイント | 内容の目安 |
|---|---|
| 安静 | できるだけ横になって休ませる。テレビやスマホは控えめに。 |
| 水分補給 | 麦茶・経口補水液・ぬるま湯などを少量ずつこまめに。 |
| 食事 | おかゆ・スープ・豆腐など、消化がよくやわらかい食事を。 |
| 睡眠 | 発熱中は昼寝もOK。体力回復が最優先。 |
感染を広げないためのお世話の仕方
子どものお世話をするときは、感染経路をできるだけ断つ工夫をしましょう。お世話をする人はできるだけ1人に限定し、不織布マスクを着用して接します。2歳以上でマスクが苦しくない子どもは、短時間でも着けられると効果的です。
おむつ替えや食事介助のあとは、石けんでの手洗いとアルコール消毒を忘れずに行います。部屋を出る前にドアノブやスイッチを軽く拭くなど、小さな積み重ねが感染予防につながります。
お子さんが安心できるように、できるだけ笑顔で接し、恐怖や不安を感じさせないよう配慮することも大切です。
マスク・換気・手洗いを家庭に取り入れる工夫
家庭内で感染を防ぐには、「空気」と「接触」の両面からの対策が必要です。
部屋の換気は30分に1回、5分程度窓を開けるのが理想的です。空気の流れをつくるため、2か所以上の窓を開けるとより効果的です。
また、部屋の湿度を50〜60%程度に保つと、喉の乾燥やウイルスの拡散を防げます。加湿器がない場合は濡れタオルを干すだけでも十分です。
手洗いは外出時だけでなく、家庭内でも「食事前」「トイレ後」「お世話後」を習慣にしましょう。
💡 ちょっとした工夫で続けやすく
- 子どもと一緒に“手洗いの歌”を歌う
- 窓を開けるタイミングをタイマーで知らせる
- マスクを外す場所を決めておく
こうしたルールを家庭全体で共有することで、自然に感染予防が習慣になります。
ごみの捨て方・洗濯・掃除の注意点
鼻をかんだティッシュや使用済みマスクは、ビニール袋に入れてしっかり縛り、密閉してから捨てます。家庭用のゴミ箱にも蓋をつけ、処理の際には手洗いを忘れないようにしましょう。
洗濯物は分けて洗う必要はありませんが、洗濯後はしっかり乾かすことが大切です。日光に当てるか乾燥機を使うと、ウイルスの残存リスクを減らせます。掃除では、ドアノブやリモコン、テーブルなど手が触れる場所を重点的に拭くと効果的です。
また、家の中が清潔で整っていると、子ども自身も安心感を持てます。体だけでなく「心の安定」も、療養を支える大切な要素です。
回復までの経過と医療機関への相談の目安
新型コロナウイルス感染症の多くは、子どもの場合軽症のまま回復するケースがほとんどです。しかし、なかには症状が長引いたり、思わぬタイミングで悪化したりすることもあります。保護者は「どこまでが自宅で様子を見てよい範囲か」「どんなときに医師へ相談すべきか」を知っておくと安心です。この章では、回復までの一般的な経過と、相談・受診の目安をわかりやすくまとめます。
水分が取れない・元気がないときの判断
体調回復の目安のひとつは、食欲と水分摂取の状態です。
発熱や喉の痛みで水分を嫌がることがありますが、半日以上ほとんど飲めない場合は注意が必要です。脱水のサインとして、以下のような変化が見られたら医療機関へ連絡しましょう。
注意したい脱水のサイン(表)
| 注意したい脱水のサイン | 状態の例 |
|---|---|
| 尿の回数・量が減っている | 半日以上おしっこが出ない、色が濃い |
| 唇・口の中が乾いている | 唾液が少ない、舌が白っぽい |
| 顔色や手足が冷たい | 体温が下がる・血の気が引いて見える |
| ぐったりして反応が鈍い | 呼びかけても反応が遅い、笑顔が少ない |
小さな子どもほど症状をうまく伝えられません。いつもより静かで元気がない、ぼんやりしているなど、「いつもと違う」様子を感じたときは、早めに相談しましょう。
発熱が続く・咳が悪化するときの対応
多くの場合、発熱は2〜3日で落ち着きますが、解熱剤を使っても熱が下がらない、5日以上発熱が続く場合は受診の目安となります。咳や鼻水が長引くこともありますが、咳が強く夜眠れない・息苦しそうな様子がある場合も、医師の判断を仰ぎましょう。
体温や症状の変化は、メモやスマートフォンのメモアプリなどに1日ごとに記録しておくと、診療時に医師へ正確に伝えやすくなります。特に、発症日・解熱日・咳の経過は再登園の判断にも役立ちます。
呼吸が苦しそう・顔色が悪いときの注意サイン
呼吸の異常は、医療機関への早急な相談・受診が必要なサインです。
肩で息をしている、胸がペコペコへこむ(陥没呼吸)、息をするたびに音がする(ゼーゼー・ヒューヒュー)などの様子があれば、ためらわず医療機関または救急相談窓口へ連絡してください。
また、唇や顔色が青白い、ぐったりして呼びかけに反応が鈍い場合も緊急対応が必要です。これらの症状が出た際は、すぐに #8000(こども医療でんわ相談) や地域の救急ダイヤルに電話し、指示に従いましょう。
🩺 迷ったら「早めの相談」
「もう少し様子を見よう」と思っている間に体調が急変するケースもあります。少しでも不安を感じたら、遠慮せず医療機関に相談するのが最善です。
迷ったときに相談できる窓口とオンライン診療の活用
近くの小児科が閉まっている時間帯でも、夜間や休日に相談できる方法はいくつかあります。代表的なものを下にまとめました。
相談先(表)
| 相談先 | 対応内容 |
|---|---|
| #8000(こども医療でんわ相談) | 看護師・医師が症状に応じて受診の要否をアドバイス |
| 各自治体の保健センター | 療養期間・登園再開の目安・家族の感染対応を案内 |
| オンライン診療アプリ「みてねコールドクター」 | 24時間365日、小児科医にスマホから相談可能。薬の処方・診断書発行にも対応 |
夜間や休日に発熱や咳が悪化しても、「みてねコールドクター」を利用すれば、自宅から医師とビデオ通話で相談できます。
登園許可証の発行や薬の配送にも対応しており、家庭でのケアを支える心強いサービスです。
予防と家庭でできる再感染対策
お子さんが回復しても、しばらくは体力や免疫が落ちやすく、再び風邪や感染症にかかるリスクがあります。家庭で無理のない範囲で生活リズムを整え、免疫を回復させていくことが大切です。この章では、再感染を防ぎながら家族全員が健康に過ごすための基本的な習慣や注意点を紹介します。
栄養・睡眠・水分を整える日常リズム
体調を整えるうえで最も大切なのは、規則正しい生活リズムです。療養明けの子どもは疲れやすく、普段よりも睡眠時間を多めに取ることが理想です。
食事はバランスを意識しながらも、「食べやすい・好きなもの」を中心にして構いません。たとえば、野菜スープや煮込みうどん、卵入りのおかゆなどは消化がよく栄養も補えます。
朝起きて太陽の光を浴びるだけでも、体内時計が整い、免疫力を高める効果があります。
生活習慣(表)
| 生活習慣 | ポイント | 予防への効果 |
|---|---|---|
| 食事 | 炭水化物+たんぱく質+野菜を意識 | 体力回復・免疫機能の維持 |
| 睡眠 | 就寝・起床時間を一定に | 自律神経を整える |
| 水分補給 | 一度に多くではなく、こまめに | 粘膜を潤し、ウイルスの侵入を防ぐ |
季節の変わり目に意識したい健康管理
季節の変わり目は気温や湿度が変化しやすく、喉や鼻の粘膜が乾燥してウイルスに感染しやすい時期です。とくに春・秋は、学校や保育園での集団生活の影響もあり、再感染が増える傾向があります。
部屋の湿度を50〜60%に保ち、空気の乾燥を防ぐことが効果的です。加湿器を使えない場合は、濡れタオルを部屋に干したり、室内に観葉植物を置くのも良い方法です。
また、手洗いやうがいを「遊びの延長」で取り入れると、子どもも抵抗なく続けられます。親子で歌いながら手を洗うなど、楽しさを感じられる工夫をしましょう。
家族内での感染予防マナー
再感染を防ぐためには、家族全員で共通のルールをもつことが大切です。子どもだけでなく大人が感染源になるケースもあるため、家庭内での予防意識を高めましょう。
🏠 家族で守りたい基本の3ルール
- 食器・タオルは共有しない
- くしゃみや咳のときはティッシュで口を覆う
- 手洗い・換気・加湿を1日数回続ける
外出時は、人の多い場所では不織布マスクを着用し、帰宅後すぐに手洗い・うがいを行います。保護者自身の体調も崩れやすいため、無理をせず「家族で支え合う」意識をもつことが大切です。
ワクチン接種・医療相談の最新情報の確認方法
感染症の状況やワクチン接種の方針は、時期や自治体によって変化します。厚生労働省や自治体の公式サイトを定期的にチェックして、最新情報を確認しておきましょう。
とくに新型コロナウイルスのワクチン接種については、年齢ごとに対象時期が異なることがあります。
また、「咳が長引く」「学校に行かせて大丈夫か分からない」といった場合は、かかりつけの小児科やオンライン診療(みてねコールドクター)を活用するのもおすすめです。自宅から医師と相談できるため、登園再開や日常生活への戻り方も安心して確認できます。
よくある質問
Q自宅療養期間はどのくらい必要ですか?
A発症日を0日目として、5日を経過し、かつ症状が軽快してから1日を経過するまでが自宅療養期間の基本です。 つまり、熱が下がっても咳や喉の痛みが続いている場合は、もう1日様子を見てからの登園・登校が安心です。 無症状の場合は、検査で陽性がわかった日を0日目として5日経過すれば、6日目から登園可能となります。
Q熱が下がっても咳や鼻水が残っているときは登園できますか?
A咳や鼻水だけが軽く残っている場合は登園できることが多いですが、咳き込みが強い・息苦しそうなどの症状がある場合はもう少し自宅で様子を見ましょう。 園や学校によって判断基準が異なるため、登園前に相談しておくと安心です。
Q家族が感染した場合、子どもは登園・登校できますか?
A家庭内に陽性者がいる場合、子どもが濃厚接触者とみなされる可能性があります。 現在は多くの自治体で「症状がなければ登園可能」とされていますが、体調の変化には十分注意してください。 咳や発熱などの初期症状が見られた時点で、すぐに登園を控えるのが安全です。
Qどんな症状のときに医療機関へ相談すべきですか?
A・次のようなサインが見られる場合は、早めに医療機関へ相談してください。 ・水分をほとんど取れない ・おしっこの回数が少ない、または色が濃い ・呼吸が速い・苦しそう ・顔色や唇が青白い ・ぐったりして反応が弱い 夜間や休日で受診が難しいときは、オンライン診療「みてねコールドクター」や#8000(こども医療でんわ相談)を活用すると安心です。
Q登園・登校再開後に気をつけることはありますか?
A登園・登校を再開してから10日間ほどは体力が完全に戻らない場合があります。 無理をさせず、早寝を心がけ、食事や水分を十分に取らせてあげましょう。 また、感染拡大を防ぐため、しばらくはマスクの着用やこまめな手洗いを続けるのが望ましいです。
安心のポイント
子どもは回復力が高いですが、体調の波があるのが自然です。
保護者が焦らず見守ることが、子どもの元気を取り戻すいちばんの近道です。
まとめ:焦らず、家庭でやさしく見守ることがいちばんの回復支援
お子さんが新型コロナウイルス陽性になったとき、突然のことで不安になるのは当然のことです。
ですが、正しい知識と落ち着いた対応があれば、家庭で無理なく回復を支えることができます。
療養期間の基本は、「発症後5日を経過し、かつ症状が軽快してから1日経過するまで」。
焦らず、子どものペースでゆっくりと体を休ませてあげましょう。
水分をこまめにとり、無理のない範囲で食事と睡眠を整えることが、いちばんの回復の近道です。
家庭では、マスク・手洗い・換気といった基本的な感染対策を続けながら、
家族全員が安心して過ごせる環境を整えていきましょう。
体調が戻っても、数日は疲れやすくなるため、登園・登校の再開も無理をせず、
「もう大丈夫」と思えるタイミングで再スタートできれば十分です。
ただ、保護者にとっては「このまま様子を見て大丈夫?」「夜中の熱が心配」と迷う場面も少なくありません。
そんなときに頼りになるのが、小児科オンライン診療アプリ「みてねコールドクター」です。
- 24時間365日、最短5分で医師の診察を受けられる
- 薬は近隣の薬局で受け取れるほか、全国配送(北海道、沖縄県、離島を除く)、一部地域では即日配送にも対応
- 登園・登校に必要な診断書や登園許可証の発行が可能
- システム利用料は無料で、健康保険や子どもの医療費助成制度にも対応
「みてねコールドクター」のアプリをインストールすれば、保護者の不安を軽減しながら、お子さんの健康を安心してサポートできます。あらかじめご家族の情報を登録しておけば、いざという時にスムーズにご利用いただけます。
家族のお守りに、みてねコールドクターをぜひご活用ください。
公式サイトはこちら:https://calldoctor.jp/
出典
- 厚生労働省:新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
- 厚生労働省:感染対策・健康や医療相談の情報
- 厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)
- 文部科学省:学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル
- 文部科学省:学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)
- 国立健康危機管理研究機構(JIHS):新型コロナウイルス感染症
- PMDA:医薬品の添付文書等を調べる(おくすり検索)
- 政府広報オンライン:健康・医療・福祉(新型コロナQ&A等)
- 東京都保健医療局:新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について
- 東京都保健医療局:小児救急医療
- 神奈川県:かながわ小児救急ダイヤル(#8000)
- 国立成育医療研究センター:新型コロナウイルス感染症Q&A(小児向け)
- こども家庭庁:保育所における感染症対策ガイドライン(PDF)
- 厚生労働省:子ども医療電話相談事業(#8000)について