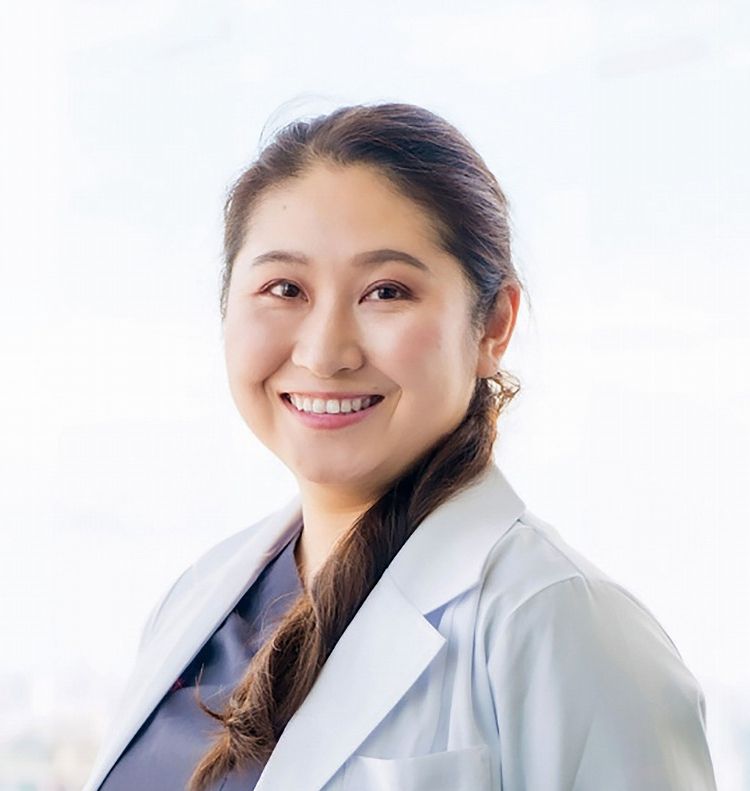子どもがやけどしたときの対処法と処置|病院を受診する目安と診療科

子どもは好奇心が旺盛で、熱いものや危険なものに思わず手を伸ばしてしまうことがあります。そのため、家庭の中で思いがけずやけどを負ってしまうことは少なくありません。熱い飲み物やスープ、炊飯器の蒸気、アイロン、さらにはカイロや湯たんぽなど、日常生活の中にやけどのリスクは潜んでいます。
万が一お子さんがやけどをしたとき、保護者が冷静に適切な対応をとれるかどうかで、その後の治り方や跡の残りやすさが大きく変わります。この記事では、家庭でできる応急処置の方法や病院を受診する目安、適切な診療科について、小児科医の視点でわかりやすく解説します。
Contents
子どものやけどの原因と起こりやすい事故
子どものやけどは、家庭内のちょっとした場面で多く発生します。特に乳幼児は皮膚が薄く、大人よりも短時間で深いやけどを負いやすいため注意が必要です。このパートでは、家庭で多いやけどの原因や年齢別の特徴を整理しながら、なぜ子どもがやけどしやすいのかを解説します。
家庭内で多いやけどの原因
家庭の中で子どもがやけどをする原因として多いのは、熱い飲み物や料理をこぼす「熱湯やけど」です。食卓の上のスープやカップ麺、炊飯器の蒸気など、身近なものが事故のきっかけになります。
また、ストーブやヒーター、アイロンやヘアアイロンなどの電化製品もやけどの原因として多く報告されています。特に冬場はカイロや湯たんぽによる「低温やけど」が増える傾向があります。見た目は軽そうでも、長時間皮膚に熱が加わることで、深い部分まで損傷してしまうことがあります。
年齢別に注意したいやけどの特徴
- 乳児期(0〜1歳):寝返りやハイハイを始めた頃は、ストーブや炊飯器に近づいて触ってしまうことが多くなります。
- 幼児期(1〜3歳):歩き始めて手が届く範囲が広がるため、テーブルの上の熱い飲み物をひっくり返す事故が増えます。
- 学童期以降:自分で調理や家電を扱う機会が増え、火や油によるやけど、花火など屋外での事故が目立ちます。
成長に伴って行動範囲が広がると同時に、やけどのリスクも変化していくため、年齢に応じた注意が必要です。
子どもの皮膚とやけどの関係
子どもの皮膚は大人よりも薄く、熱の影響を受けやすい特徴があります。同じ温度のお湯に触れた場合でも、大人は軽い赤み程度で済むのに対し、子どもは短時間で深いやけどに進行してしまうことがあります。
さらに、体の表面積に占めるやけどの範囲が広くなりやすいため、大人よりも脱水や感染のリスクが高まります。このため「少しの範囲だから大丈夫」と安易に考えず、子どものやけどは常に注意して観察することが大切です。
すぐに行うべき応急処置の方法
子どもがやけどをしたとき、保護者が最初に行う応急処置はとても重要です。ここで適切に対応できるかどうかが、その後の治り方や跡の残りやすさに直結します。このパートでは「冷やす」を中心とした基本の流れ、水ぶくれができたときの扱い、そしてやってはいけない注意点について解説します。
流水で冷やす際の正しい手順
やけどを負ったら、まずは落ち着いて流水で冷やしましょう。水道から出る弱めの流水を直接やけど部分に当て、15〜30分を目安に冷やし続けます。痛みが和らぐまで続けるのが基本です。服を着ている場合は、まず服の上から冷やし、十分に冷えた後で脱がせてください。皮膚に服が貼りついている場合は、無理に剥がさず、周囲をハサミで切って受診時に対応するのが安全です。
水ぶくれ(水疱)ができた場合の扱い
やけどの深さによっては、水ぶくれ(水疱)ができることがあります。これは皮膚が損傷し、体が自然に患部を守ろうとしているサインです。水ぶくれは決して自分で潰してはいけません。膜が外部から細菌が入るのを防いでいるため、破ると感染のリスクが高まり、治りが遅くなり、跡が残る原因になります。
もし破れてしまった場合は、清潔なガーゼで軽く覆い、速やかに医療機関を受診してください。
やってはいけない対処法と注意点
やけどをしたとき、昔からの民間療法で「味噌やアロエを塗る」といった方法を耳にすることがあります。しかし、これらは科学的根拠がなく、かえって感染を引き起こす原因になります。
- 氷や保冷剤を直接当てる:冷えすぎて血流が悪くなり、治りが遅くなる可能性があります。
- 消毒液を使う:刺激で皮膚を傷め、自然な回復を妨げることがあります。
- 油や軟膏を勝手に塗る:熱がこもって悪化したり、感染の原因になることがあります。
家庭での応急処置は「流水で冷やす」「清潔に覆う」の2点に絞ることが最も安全で確実です。
病院を受診する目安と重症度の見分け方
やけどは見た目が軽そうに見えても、実は皮膚の深いところまで損傷していることがあります。子どもの場合は皮膚が薄く、短時間で重症化することがあるため、「どの程度なら家庭で様子を見ても良いのか」「どのような場合に受診すべきか」を知っておくことが大切です。このパートでは、受診が必要となる範囲や部位、やけどの深さによる重症度の目安について説明します。
受診が必要となるやけどの範囲と部位
やけどの大きさが子どもの手のひらよりも広い場合は、必ず受診してください。子どもの手のひらは体表面積の約1%に相当し、それ以上の広さになると感染や脱水のリスクが高まります。
また、顔・関節・手足・陰部などは機能や見た目に影響が残りやすいため、範囲が小さくても専門的な治療が必要になります。特に関節部分は皮膚が縮んで動かしにくくなる(瘢痕拘縮)リスクがあるため注意が必要です。
重症度の目安|Ⅰ度・Ⅱ度・Ⅲ度の違い
やけどの深さは大きく3つに分けられます。
| 重症度 | 特徴 | 痛み |
|---|---|---|
| Ⅰ度 | 皮膚が赤くなる程度。日焼けのような状態。 | 強い痛みあり |
| Ⅱ度 | 水ぶくれができる。浅い場合は跡が残りにくいが、深いと治りに時間がかかる。 | 強い痛みあり |
| Ⅲ度 | 皮膚が白や黒に変化し、感覚がなくなる。皮膚の奥深くまで損傷。 | 痛みが少ないこともあるが危険 |
Ⅰ度であれば家庭での冷却と観察で回復しますが、Ⅱ度以上は必ず受診し、Ⅲ度の疑いがある場合は救急外来を受診してください。
救急受診を考えるべき症状と状態
次のような場合は夜間や休日でも迷わず救急受診を検討してください。
- 子どもがぐったりしている、意識がもうろうとしている
- 顔や呼吸に関わる部位にやけどを負った
- 広範囲にわたるⅡ度以上のやけど
- 電気やけど、化学薬品によるやけど
- 水分が取れず、おしっこが出ていない
外見だけでは判断できないケースもあるため、少しでも迷う場合は受診することが安心につながります。
受診する診療科と治療の流れ
子どもがやけどをしたとき、どの診療科を受診すべきか迷うことも少なくありません。やけどの程度や部位によって適切な診療科が異なるため、状況に応じた選択が大切です。このパートでは、小児科・皮膚科・形成外科・救急外来それぞれの特徴と役割について解説します。
小児科での診療と判断のポイント
まず相談先として最も身近なのは小児科です。かかりつけ医であれば子どもの成長や体調を把握しているため安心して相談できます。軽いやけどであればその場で治療が行われますし、専門的な治療が必要な場合は適切な医療機関を紹介してもらえます。特に乳幼児の場合は、皮膚が薄く重症化しやすいため、まず小児科を受診するのが無難です。
皮膚科・形成外科での専門的な治療
皮膚科や形成外科は、やけどの専門的な治療を行う診療科です。水ぶくれが広範囲に及ぶ場合や、顔や関節など跡を残したくない部位のやけどでは、形成外科での治療が推奨されます。皮膚の再生を助ける処置や、傷跡を最小限にするケアについても専門的な知識を持っているため、必要に応じて紹介状をもらい受診するとよいでしょう。
救急外来を受診するケース
夜間や休日にやけどを負った場合や、範囲が広い、皮膚が白く変色している、電気や化学薬品によるやけどなどは、迷わず救急外来を受診してください。子どもは体表面積に比べて体が小さいため、大人に比べて短時間で全身状態が悪化しやすいのが特徴です。救急外来では全身管理を含めた迅速な処置が受けられるため、命や今後の生活に関わる後遺症を防ぐためにも早めの判断が必要です。
家庭でできるケアと再発予防
やけどを負った後は、医療機関での治療に加えて、家庭でのケアがとても大切です。適切なホームケアを行うことで、治りが早くなり、跡が残るリスクを減らすことができます。また、子どものやけどは家庭内での事故が多いため、日常生活の中で予防を意識することも欠かせません。
冷却後の保護とガーゼの使い方
十分に冷却した後は、患部を清潔に保ち、乾燥や感染を防ぐことが大切です。清潔なガーゼやタオルでやさしく覆い、摩擦や刺激を避けましょう。市販のラップを使うと一時的に乾燥を防げますが、必ず医師の診察を受けた上で使用することをおすすめします。水ぶくれがある場合は、潰さずそのまま保護してください。
日常生活での注意点とケア
入浴は医師の指示に従いましょう。軽いやけどの場合は短時間であれば入浴可能ですが、石けんで強くこすったり熱いお湯に浸かったりするのは避けるべきです。衣服は柔らかい綿素材を選び、肌への刺激を減らします。かゆみや痛みが強いときは、冷たいタオルで軽く冷やすと楽になることがあります。
子どものやけどを防ぐための家庭での工夫
子どものやけどは一瞬の油断で起こります。予防のためには、日常生活の中での工夫が重要です。
- テーブルの端に熱い飲み物を置かない
- 炊飯器や電気ポットを手の届かない位置に置く
- アイロンやヘアアイロンは使った後すぐに片づける
- 冬場はカイロや湯たんぽを直接肌に当てない
こうした小さな工夫が、子どもの大きな事故を防ぐことにつながります。
よくある質問
Q子どもがやけどをした直後にまずやることは?
Aやけどをしたら、すぐに流水で15〜30分冷やすことが最優先です。氷や保冷剤を直接当てるのは避けましょう。冷やした後は清潔なガーゼで覆い、様子を見ながら必要なら受診してください。
Q水ぶくれができた場合に家庭で処置してよい?
A水ぶくれは皮膚を守る役割があるため、絶対に潰してはいけません。自分で破ると感染のリスクが高まり、治りが遅くなります。破れてしまった場合も、ガーゼで覆って早めに受診することが安心です。
Q顔や関節にやけどをしたときの注意点は?
A顔や関節は跡が残りやすく、皮膚が縮んで動きにくくなるリスクもあります。範囲が小さくても、必ず小児科や形成外科を受診してください。
Q救急外来を受診した方がよいのはどんな時?
A子どもがぐったりしている、広範囲に水ぶくれがある、皮膚が白や黒に変色している場合は救急外来を受診してください。また、電気やけどや化学やけどは見た目以上に重症化する可能性があるため、迷わず救急へ。
Q再発予防のために家庭でできる工夫は?
Aテーブルの端に熱い飲み物を置かない、炊飯器やポットを子どもの手が届かない位置に置く、カイロや湯たんぽは直接肌に触れさせないなど、日常生活での小さな配慮が大きな事故を防ぎます。
まとめ|落ち着いた対処と早めの受診が安心
子どものやけどは一瞬の不注意で起こりますが、その後の対処で大きく経過が変わります。まずは慌てずに流水でしっかりと冷やし、清潔に覆うことが基本です。そして、範囲が広い場合や水ぶくれができた場合、顔や関節など跡が残りやすい部位の場合は、ためらわずに受診してください。
小児科をはじめ、皮膚科や形成外科、救急外来といった医療機関は、それぞれの状況に応じて適切な治療を行ってくれます。自己判断で処置を続けるよりも、早めに相談することが子どもの未来のためにも安心です。
また、日常生活の中でやけどのリスクを減らす工夫を心がけることで、事故を防ぐことができます。熱い飲み物の扱いや調理家電の配置、冬場のカイロや湯たんぽの使用など、小さな工夫が子どもの安全につながります。
さらに、夜間や休日に迷ったときは、オンライン診療サービスを活用するのも一つの方法です。
そんな時に頼りになるのがオンライン診療アプリ「みてねコールドクター」です。
- 24時間365日、最短5分で医師の診察を受けられる
- 薬は近隣の薬局で受け取れるほか、全国配送(北海道、沖縄県、離島を除く)、一部地域では即日配送にも対応
- 登園・登校に必要な診断書や登園許可証の発行が可能
- システム利用料は無料で、健康保険や子どもの医療費助成制度にも対応
「みてねコールドクター」のアプリをインストールすれば、保護者の不安を軽減しながら、お子さんの健康を安心してサポートできます。あらかじめご家族の情報を登録しておけば、いざという時にスムーズにご利用いただけます。
家族のお守りに、みてねコールドクターをぜひご活用ください。
公式サイトはこちら:https://calldoctor.jp/