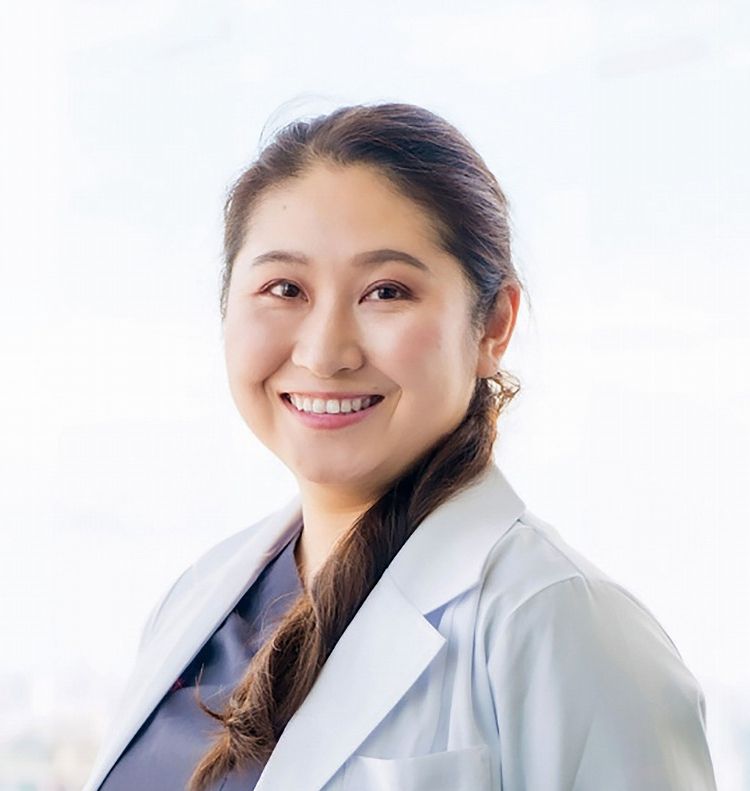子どもの嘔吐や下痢:受診のタイミングと原因、小児科に行く目安

子どもが突然吐いたり、下痢が続いたりすると、保護者の方はとても心配になりますよね。「食べ過ぎただけかも?」「病院へ行ったほうがいいの?」と迷う場面も多いでしょう。実際、子どもの嘔吐や下痢は日常的によく見られる症状ですが、見極めを誤ると脱水など危険な状態に進むこともあります。
大切なのは、原因を正しく理解し、家庭でできるケアを行いながら、適切なタイミングで小児科を受診することです。この記事では、子どもの嘔吐や下痢の主な原因、家庭での対処法、脱水のサイン、そして病院を受診する目安をわかりやすく解説していきます。
子どもの嘔吐や下痢の主な原因と特徴
子どもの嘔吐や下痢は、感染による胃腸炎が圧倒的に多くを占めます。ただし、食べ過ぎや便秘など一時的な原因によることもあり、まれには腸重積といった緊急性の高い病気が隠れていることもあります。ここでは、主な原因と特徴を整理します。
ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス・ロタウイルスなど)
冬場に特に流行しやすいのがウイルス性胃腸炎です。ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどが代表的で、いわゆる「お腹の風邪」と呼ばれることもあります。突然の嘔吐から始まり、その後水のような下痢や発熱を伴うのが特徴です。
ロタウイルスは特に乳幼児に多く、白っぽい水様便が出ることがあります。家庭内で一人が感染すると兄弟姉妹に広がりやすく、集団生活でも流行を引き起こすため注意が必要です。
細菌性胃腸炎と食中毒による下痢・嘔吐
サルモネラ菌やカンピロバクター、病原性大腸菌(O-157など)による細菌性胃腸炎は、主に食中毒として発症します。発熱や強い腹痛を伴い、便に血が混じることもあります。特に夏場に多く、肉や生ものの摂取がきっかけになることが多いです。
症状が激しい場合はすぐに医療機関を受診する必要があります。ウイルス性とは異なり、抗菌薬が必要となるケースもあるため、自己判断で様子を見続けないようにしましょう。
その他の原因|食べ過ぎ・便秘・腸重積など
子どもの嘔吐や下痢は必ずしも感染症だけが原因ではありません。食べ過ぎや飲み過ぎによる一時的な嘔吐、便秘によって吐いてしまうこともあります。また、食物アレルギーが関与している場合もあり、原因食材を食べた直後に嘔吐が起こることもあります。
さらに注意すべきは腸重積です。腸の一部が別の腸に入り込むことで起こる病気で、激しい腹痛と嘔吐を繰り返し、血便が出ることもあります。進行すると命に関わるため、疑わしい場合はすぐに救急受診が必要です。
家庭でできる基本の対処法
子どもの嘔吐や下痢には特効薬がなく、多くの場合は体がウイルスや細菌を排出するのを待つことになります。そのため、家庭でのケアの中心は「脱水を防ぐこと」と「胃腸への負担を減らすこと」です。このパートでは、水分補給の工夫、食事再開の目安、そして二次感染を防ぐための注意点について解説します。
水分補給のコツと経口補水液の使い方
最も大切なのは水分補給です。脱水を防ぐためには、経口補水液(ORS)が最も適しています。水分だけでなくナトリウムやカリウムといった電解質を一緒に補えるため、点滴が必要な状況になるのを防いでくれます。
飲ませ方のポイントは「少量をこまめに」です。スプーン1杯程度を5〜10分おきに与えるのが理想で、一度に多く与えると刺激になって再び吐いてしまいます。嘔吐直後は胃を休ませるため、30分から1時間ほどあけてから補給を始めましょう。
食事を再開するタイミングと選び方
食欲が戻るまでは無理に食べさせる必要はありません。水分補給を優先し、少しずつ元気が出てきたら消化に良い食事から再開します。
- おかゆ
- よく煮込んだうどん
- すりおろしりんご
- 豆腐や茶碗蒸し
- 野菜スープ
これらは胃腸にやさしく、エネルギーや水分を補うのに適しています。油っこいものや乳製品、柑橘系のジュースは下痢を悪化させることがあるため避けてください。
二次感染を防ぐための家庭での工夫
嘔吐物や下痢の便には多くのウイルスや細菌が含まれており、適切に処理しないと家族に感染が広がってしまいます。処理の際は必ず使い捨ての手袋とマスクを着用しましょう。汚れた床や衣服は、次亜塩素酸ナトリウムを薄めた消毒液(塩素系漂白剤を希釈したもの)で拭き取ると安心です。
また、タオルや食器の共用を避け、しっかりと手洗いを徹底することも大切です。特にきょうだいや保護者への二次感染を防ぐことが、回復を早める大きなポイントとなります。
脱水症状に注意|見逃してはいけないサイン
子どもの嘔吐や下痢で最も注意しなければならないのが脱水症状です。体の水分が急速に失われることで全身の働きに影響を与え、放置すると命に関わることもあります。特に乳幼児は体内の水分量が多く、短時間で脱水に陥りやすいため注意が必要です。このパートでは、脱水の具体的なサインと、赤ちゃん・幼児で見逃しやすい点を整理します。
脱水を疑うときの具体的な症状
次のようなサインが見られる場合は、すでに脱水が始まっている可能性があります。
- 機嫌が悪く、ぐずりやすい、または元気がなく遊ばない
- 唇や口の中が乾いている
- 泣いても涙が出ない
- 目がくぼんで見える
- おしっこの量や回数が減る(半日以上出ていない場合は要注意)
これらが複数当てはまる場合は、家庭での水分補給だけでは追いつかないことがあります。点滴など医療的な補給が必要になるため、早めに受診してください。
赤ちゃん・幼児で特に気をつけたいこと
赤ちゃんは自分で「喉が渇いた」と訴えることができず、症状が進んでから気づくケースが少なくありません。おむつの濡れ具合は大切な目安になります。8時間以上おしっこが出ていない場合は、受診を考えてください。
また、授乳中の赤ちゃんでは母乳やミルクの飲みが悪くなることがあります。飲む量が極端に減ったり、吐いてしまって補給できない場合は脱水が進行しやすいため、早めの対応が必要です。
幼児では「お茶を飲みたがらない」「だるそうに寝てばかりいる」といった変化も重要なサインです。元気や食欲の有無を観察することが、脱水の早期発見につながります。
受診のタイミングと病院に行く目安
子どもの嘔吐や下痢は多くの場合、家庭でのケアで回復しますが、なかには早急な受診が必要なケースもあります。重要なのは「家庭で様子を見てもよいのか」「すぐに病院へ行くべきか」を見極めることです。このパートでは、受診が必要なサインを具体的に整理します。
すぐに受診すべき症状(血便・ぐったり・繰り返す嘔吐)
夜間や休日であっても、以下の症状がある場合は救急外来を含めてすぐに医療機関を受診してください。
- ぐったりして意識がもうろうとしている
- 呼びかけに反応しにくい
- 血便が出た(イチゴジャムのような赤い便、黒っぽい便も含む)
- コーヒーかすのようなものや血液を吐いた
- 激しい腹痛を伴い、不機嫌に泣くのとけろっとするのを繰り返す(腸重積を疑う)
- 水分をほとんど受け付けず、嘔吐を繰り返している
- 半日以上おしっこが出ていない
- けいれんを起こした
診療時間内に小児科を受診するケース
命に関わる危険は少なくても、次のような症状が続く場合は診療時間内に受診してください。
- 嘔吐や下痢が数日続いている
- 発熱があり、下痢や嘔吐とともに元気がない
- 食欲がなく、食べられる量が少ない
- 家庭でのケアをしても改善しない
- 保護者が「普段と違う」と強く感じる
保護者が判断しやすい目安のまとめ
以下の表に、受診のタイミングを整理しました。
| 状態・症状 | 対応の目安 |
|---|---|
| 軽い嘔吐や下痢、元気がある | 水分補給を中心に家庭で様子を見る |
| 嘔吐や下痢が続き、食欲がない | 診療時間内に小児科を受診 |
| 血便・意識がもうろう・ぐったり | 夜間や休日でも救急外来を含めてすぐ受診 |
| 半日以上おしっこが出ていない | 脱水の危険あり、早めに受診 |
このように整理しておくと、保護者が迷ったときにも冷静に判断しやすくなります。
予防と家庭でのケアのポイント
子どもの嘔吐や下痢は一度かかると家族内に広がりやすく、看病する保護者にとっても大きな負担になります。症状を軽くするための家庭での工夫と、再発や感染を防ぐための予防策を知っておくことが大切です。
嘔吐や下痢があるときの家庭での衛生管理
嘔吐物や便には多くのウイルスや細菌が含まれているため、適切な処理が必要です。処理をするときは必ず使い捨ての手袋とマスクを着用し、汚れた場所は塩素系漂白剤を薄めた消毒液で拭き取りましょう。布団や衣類に付着した場合は、熱湯消毒や塩素系漂白剤の使用が有効です。
また、処理後は必ず石けんでしっかりと手を洗い、タオルの共用は避けてください。家庭内感染を防ぐ第一歩は「手洗いの徹底」です。
手洗い・消毒で感染拡大を防ぐ方法
嘔吐や下痢の原因となるノロウイルスやロタウイルスは、非常に感染力が強いことで知られています。流水と石けんを使った30秒程度の手洗いをこまめに行うことが重要です。アルコール消毒は効果が弱いため、特にノロウイルスの場合は石けんと流水での洗浄が基本となります。
ドアノブやトイレのレバーなど、手が触れやすい場所もこまめに消毒すると安心です。
元気が戻った後の食事と生活リズムの整え方
嘔吐下痢が落ち着き、元気や食欲が戻ってきたら、徐々に普段の食事へ移行していきます。回復期におすすめなのは、おかゆや煮込みうどん、柔らかく煮た野菜など、消化に優しいメニューです。無理にたくさん食べさせず、少量ずつ様子を見ながら進めましょう。
体調が整ってきたら、生活リズムも少しずつ通常に戻していきます。睡眠をしっかりとり、軽い外遊びから始めることで回復がスムーズになります。
よくある質問
QQ1. 嘔吐や下痢のときに水分を飲ませる量とタイミングは?
A一度にたくさん与えると吐きやすくなるため、スプーン1杯程度を5〜10分おきに少しずつ与えるのが基本です。経口補水液が最適ですが、なければ麦茶や湯冷ましも使えます。
QQ2. 嘔吐や下痢が続くとき家庭で様子を見てもいい?
A元気があり水分を取れている場合は家庭で様子を見ても大丈夫です。ただし、ぐったりしている、血便がある、水分がとれない場合はすぐに受診が必要です。
QQ3. 嘔吐や下痢で血便が出たときはどうする?
A血便は細菌感染や腸重積など重大な病気のサインであることがあります。夜間や休日であっても、ためらわずに病院を受診してください。
QQ4. 嘔吐や下痢のときにミルクや母乳は続けてよい?
A母乳は消化によく水分補給にもなるため、可能であれば続けて構いません。ミルクは少量ずつ与え、吐くようであれば一時的に間隔をあけてください。
QQ5. 嘔吐や下痢は何日くらいで治るのが一般的?
Aウイルス性胃腸炎であれば、多くは数日から1週間程度で回復します。ただし症状の強さや原因によって経過は異なるため、不安な場合は小児科に相談してください。
まとめ|子どもの嘔吐や下痢は脱水と受診タイミングに注意
子どもの嘔吐や下痢は、ほとんどの場合がウイルスや細菌による胃腸炎で、家庭でのケアによって自然に回復していきます。しかし、最も注意すべきは脱水症状であり、短時間で進行することがあるため、保護者が早く気づいて対応することが大切です。
水分補給は「少量をこまめに」が基本で、経口補水液をうまく活用すると安心です。食事は無理をせず、消化にやさしいものから少しずつ再開しましょう。嘔吐物や下痢の処理を丁寧に行うことで、家庭内での二次感染も防げます。
一方で、血便やぐったりした様子、水分がとれない状態など、危険なサインがあるときは迷わず医療機関を受診してください。保護者の「なんとなくいつもと違う」という直感も大切な判断材料です。
不安なときは一人で抱え込まず、医師に相談することが安心につながります。
そんな時に頼りになるのがオンライン診療アプリ「みてねコールドクター」です。
- 24時間365日、最短5分で医師の診察を受けられる
- 薬は近隣の薬局で受け取れるほか、全国配送(北海道、沖縄県、離島を除く)、一部地域では即日配送にも対応
- 登園・登校に必要な診断書や登園許可証の発行が可能
- システム利用料は無料で、健康保険や子どもの医療費助成制度にも対応
「みてねコールドクター」のアプリをインストールすれば、保護者の不安を軽減しながら、お子さんの健康を安心してサポートできます。あらかじめご家族の情報を登録しておけば、いざという時にスムーズにご利用いただけます。
家族のお守りに、みてねコールドクターをぜひご活用ください。
公式サイトはこちら:https://calldoctor.jp/