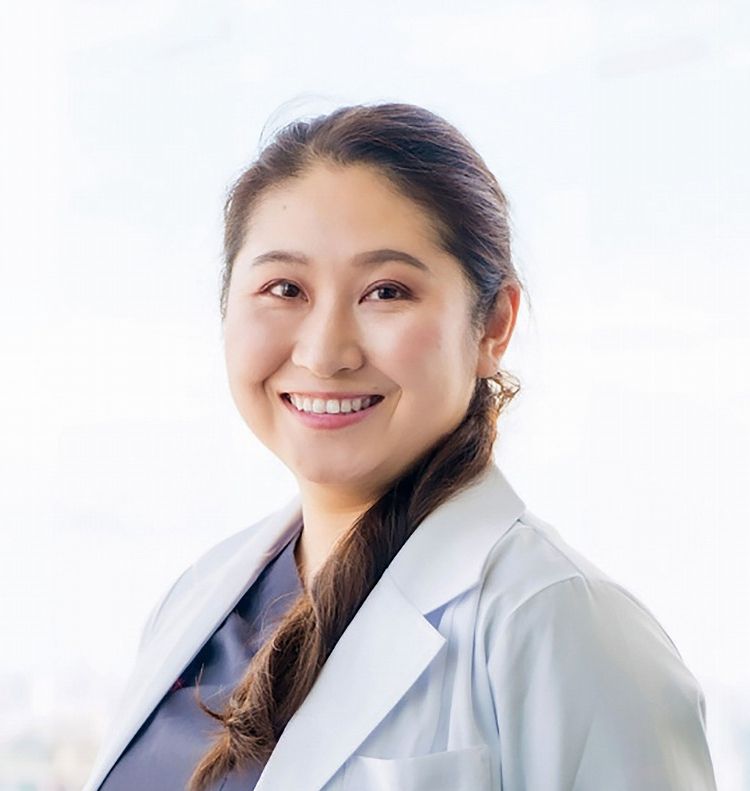ヘルパンギーナ・手足口病・溶連菌感染症の違いを解説 【夏の子ども感染症の見分け方】

夏の時期になると、保育園や幼稚園に通う子どもたちの間でよく流行する感染症があります。その代表格が「手足口病」「ヘルパンギーナ」「溶連菌感染症」の3つです。いずれも発熱や喉の痛みといった似た症状から始まるため、保護者にとっては区別がつきにくいことが少なくありません。しかし、原因となる病原体や症状の出方、治療法や登園再開の目安にはそれぞれ違いがあります。特に溶連菌感染症は細菌が原因で抗菌薬による治療が必要になるため、早めに見分けることが大切です。本記事では、3つの感染症の症状と特徴を比較し、見分け方のポイントや注意点をわかりやすく解説します。
Contents
手足口病の症状と特徴を解説
手足口病は主にエンテロウイルスによるウイルス感染症で、夏に子どもの間で流行しやすい病気です。多くは発熱が軽く、手のひら・足の裏・口の中にできる水疱性の発疹が特徴です。口内の痛みで食欲低下や脱水につながることがあるため、こまめな水分補給が重要です。通常は対症療法で数日〜1週間ほどで回復しますが、まれに合併症が起こることもあります。ここでは原因ウイルスと発症の仕組み、症状の全体像、そして注意すべきポイントを整理します。
主な原因ウイルスと発症の仕組み
手足口病の原因はエンテロウイルス(代表例:コクサッキーウイルスA16、エンテロウイルス71 など)です。飛沫感染、接触感染、排便後の不十分な手洗いによる糞口感染で広がります。潜伏期間はおよそ3〜5日。のど(咽頭)や腸で増えたウイルスが血流に乗って皮膚や口腔粘膜に達し、小さな水疱や口内炎を作ります。乳幼児は自分で衛生管理が難しく、保育園・幼稚園などの集団生活で拡大しがちです。ウイルスは症状改善後もしばらく便から排出されるため、回復期も手洗いを続けることが感染予防に有効です。
発熱・発疹・口の中の水疱の症状
発熱は38℃以下の微熱が多く、ときに発熱がないこともあります。最も特徴的なのは手・足・口に現れる発疹で、おしりやひざに出る場合もあります。口腔内の水疱が破れて潰瘍になると強い痛みが生じ、食事や水分がとりにくくなるのが難点です。発熱は通常3〜5日で落ち着き、全身状態も回復へ向かいますが、発疹は1〜3週間ほど残ることがあります。かゆみは軽度〜中等度で、皮膚症状そのものよりも口の痛みによる食欲低下や脱水への配慮が重要です。刺激の少ない冷たい飲食物を選び、少量ずつこまめな補給を心がけましょう。
子どもに多い合併症と注意点
大半は自然軽快しますが、まれに無菌性髄膜炎や脳炎、心筋炎などの合併症が報告されています(特にEV71関連)。次のような場合は小児科への受診を優先してください。高熱(38.5〜39℃以上)が続く、ぐったりして反応が弱い、水分がほとんど取れない、嘔吐を繰り返す、けいれんがある、呼吸が速い・苦しそうなどです。保育園・幼稚園では登園基準が設けられていることが多く、発熱が下がり、口の痛みが改善して普段どおりに食べて遊べる状態が再開の目安になります。家庭内・園内での手洗い徹底と共有物の衛生管理が、感染拡大の抑制に役立ちます。
受診を急いだ方が良いサイン
| サイン | 状況の例 |
|---|---|
| 高熱が続く | 38.5〜39℃以上が数日続く |
| 元気がない | ぐったりして反応が弱い |
| 水分不足 | 水分をほとんど取れない、尿が減っている |
| 神経症状 | 嘔吐を繰り返す、けいれんがある |
| 呼吸異常 | 呼吸が速い、苦しそう、顔色が悪い |
ヘルパンギーナの症状と特徴を解説
ヘルパンギーナも、毎年夏に流行する代表的な子どものウイルス感染症です。主にコクサッキーウイルスA群によって引き起こされ、突然の高熱と喉の奥にできる小さな水疱が特徴です。発症は急で、元気だった子どもが急に39℃以上の熱を出し、強い喉の痛みで食欲が落ちるケースが多く見られます。発疹が手足に出る手足口病とは異なり、口腔内の変化が中心になるのが大きな特徴です。ここでは、発症の理由、他の夏風邪との違い、そして重症化する場合の注意点について解説します。
急な高熱と喉の水疱が現れる理由
ヘルパンギーナは潜伏期間が2〜4日と短く、突然の発熱で始まることが多い病気です。熱は38〜40℃まで上がることがあり、発症から1〜2日で喉の奥(口蓋垂周囲)に小さな水疱や口内炎が現れます。これが破れると強い痛みを伴い、子どもは水分や食事をとるのを嫌がるようになります。特に乳幼児では脱水症状に注意が必要です。
他の夏風邪との違いと見分け方
手足口病と混同されることもありますが、発疹が手足に出ないのが大きな違いです。また、溶連菌感染症と比べると、溶連菌では「いちご舌」や全身の細かい発疹が出ますが、ヘルパンギーナでは喉の奥の水疱に限られます。
ヘルパンギーナ → 高熱+喉の奥に水疱
手足口病 → 微熱〜中等度の熱+手・足・口の発疹
溶連菌感染症 → 高熱+いちご舌+全身の発疹
重症化した場合の注意点
多くは3〜5日ほどで自然に解熱しますが、一部の子どもでは熱性けいれんを起こしたり、まれに無菌性髄膜炎や脳炎を合併することがあります。次のような場合は小児科や救急外来をすぐに受診してください。
受診を急いだ方が良いサイン
| サイン | 状況の例 |
|---|---|
| 高熱が続く | 39℃以上の発熱が3日以上続く |
| 水分不足 | 水分をほとんど取れず、尿が減っている |
| 神経症状 | 嘔吐を繰り返す、熱性けいれんがある |
| 呼吸異常 | 呼吸が苦しそう、顔色が悪い、ぐったりしている |
溶連菌感染症の症状と特徴を解説
溶連菌感染症は、A群溶血性レンサ球菌という細菌が原因で起こる感染症です。夏風邪として扱われることもありますが、実際にはウイルスではなく細菌による病気であるため、治療に抗菌薬(抗生物質)が必要になります。発症は主に幼児から学童期に多く、高熱と強い喉の痛みを伴うのが特徴です。さらに全身に細かい発疹が出ることもあり、見た目の症状が手足口病やヘルパンギーナと混同されやすい点に注意が必要です。ここでは、原因や診断の流れ、典型的な症状、そして合併症予防の重要性について解説します。
細菌感染による原因と診断の流れ
溶連菌感染症は、飛沫感染や接触感染によって広がります。発症すると38℃以上の高熱が出て、喉の強い痛みや腫れが現れます。診断には小児科での迅速検査キットが用いられ、数分で結果がわかるのが特徴です。ウイルス性の夏風邪と異なり、原因が細菌であるため抗菌薬治療が不可欠です。
喉の痛み・いちご舌・発疹の特徴
喉は真っ赤に腫れ、扁桃腺に白い膿(滲出物)が付くことがあります。また、舌が赤くブツブツになる「いちご舌」は溶連菌感染症に特徴的な所見です。さらに、紙やすりのようなざらざらした細かい発疹が首や胸から全身に広がることもあります。発疹はかゆみを伴う場合もあり、見た目だけでは手足口病やアトピー性皮膚炎と紛らわしいことがあります。
合併症を防ぐために大切な治療
最も重要なのは、処方された抗菌薬を必ず最後まで飲み切ることです。症状が軽快しても途中で服用をやめると、再発のリスクやリウマチ熱、急性糸球体腎炎といった重大な合併症を引き起こす可能性があります。家庭では安静に過ごし、十分な水分補給と消化の良い食事を心がけると良いでしょう。登園や登校の再開については、抗菌薬を内服開始後24時間が経過し、発熱がなく全身状態が安定していることが一般的な目安とされています。
受診を急いだ方が良いサイン
| サイン | 状況の例 |
|---|---|
| 高熱が続く | 38℃以上の発熱が数日続く |
| 喉の異常 | 強い痛みで食事や水分がとれない、息苦しさがある |
| 発疹の異常 | 全身に発疹が広がり、かゆみや痛みが強い |
| 合併症の疑い | 顔や足のむくみ、血尿、関節痛などが見られる |
三大感染症の違いと見分け方
手足口病、ヘルパンギーナ、溶連菌感染症はいずれも子どもに多くみられる夏の感染症ですが、原因となる病原体や症状の出方には明確な違いがあります。特に「発疹の出る部位」「喉や舌の変化」「発熱の特徴」を整理して理解することで、見分けやすくなります。ただし、自己判断だけで確定するのは難しく、あくまで参考の目安としてとらえ、迷ったときは医療機関での診断を受けることが大切です。ここでは、それぞれの病気の症状を比較しながら見分け方を解説します。
発疹や水疱の出る部位の違い
最も分かりやすい違いは発疹の出る場所です。手足口病では「手のひら・足の裏・口の中」、ヘルパンギーナは「喉の奥」、溶連菌感染症では「全身に広がる赤い細かい発疹」が現れます。この違いを知っておくと、初期段階で区別しやすくなります。
| 病気名 | 発疹・水疱の特徴 |
|---|---|
| 手足口病 | 手・足・口に水疱性の発疹。お尻や膝に出ることもある |
| ヘルパンギーナ | 喉の奥に小さな水疱や口内炎が出る |
| 溶連菌感染症 | 首や胸から全身に広がる赤い細かい発疹(かゆみを伴うことも) |
喉と舌の状態で見分けるポイント
喉の痛みは3つの病気に共通しますが、症状の現れ方が異なります。手足口病では口全体に口内炎ができやすく、食事や水分がしみにくくなります。ヘルパンギーナでは喉の奥の水疱や潰瘍が強い痛みを伴います。溶連菌感染症は扁桃腺が赤く腫れ、白い膿が出ることも。さらに「いちご舌」が特徴的であり、見分けるポイントになります。
発熱の特徴で比較する方法
発熱のパターンもそれぞれ異なります。手足口病は微熱〜中等度の熱で、発熱がないこともあります。ヘルパンギーナは39℃以上の急な高熱が出やすく、溶連菌感染症は38℃以上の高熱が数日続くことがあります。熱の高さと持続期間を観察することが、診断の手がかりになります。
大人や家庭内で感染した場合の注意
これらの感染症は子どもに多いものですが、大人も感染することがあります。大人がかかると症状が重く出ることがあり、特に喉の痛みや発熱で日常生活に支障をきたす場合があります。家庭内で感染を防ぐためには、手洗いやうがいを徹底し、タオルや食器を共用しないことが大切です。症状がある場合は無理に仕事や外出をせず、早めに医療機関を受診しましょう。
治療と予防:家庭でできること
夏に流行する三大感染症は、いずれも子どもにとって負担の大きい病気です。しかし、原因がウイルスか細菌かによって治療の方法は異なります。手足口病やヘルパンギーナはウイルス性のため特効薬はなく、主に対症療法で体調を整えて回復を待ちます。一方、溶連菌感染症は細菌が原因であるため、抗菌薬(抗生物質)による治療が必要です。家庭では症状に合わせて水分補給や食事の工夫を行い、体力を落とさないことが重要です。ここでは、代表的な治療の考え方と、家庭や園でできる予防法について解説します。
手足口病・ヘルパンギーナの対症療法
この2つはウイルスが原因のため、根本的に治す薬はありません。医師の指示に従い、解熱剤や鎮痛薬を使いながら症状を和らげるのが中心です。口の中に痛みがある場合は、冷たくて刺激の少ない食べ物(ゼリーやプリン、アイスなど)が食べやすく、脱水予防につながります。休養と十分な睡眠が最も大切な治療になります。
溶連菌感染症の抗菌薬治療
溶連菌感染症は抗菌薬が有効であり、処方された薬を必ず飲み切ることが合併症を防ぐ上で不可欠です。症状が改善しても服薬を中断すると、再発やリウマチ熱、腎炎などの重い合併症につながる恐れがあります。抗菌薬を開始して24時間経過すれば登園・登校が可能になることが多いですが、必ず医師の指示を確認してください。
家庭でできる予防と手洗い・うがい
感染を防ぐ基本は手洗いです。特にトイレの後、食事の前、おむつ交換後などに石けんを使って丁寧に洗うことが大切です。うがいも効果的で、のどの粘膜を清潔に保つ助けになります。また、タオルや食器の共用は避け、こまめに換気を行うことも予防に役立ちます。
保育園や幼稚園での注意点
園生活では子ども同士の距離が近く、どうしても感染が広がりやすい環境です。流行期には園が独自に感染症対策を強化することもあります。保護者としては、登園前に子どもの体調をよく観察し、熱や発疹がある場合は無理をさせず休ませることが大切です。園と連携をとり、必要に応じて登園届や医師の診断書を準備しておくと安心です。
よくある質問
Q手足口病・ヘルパンギーナ・溶連菌感染症はどう見分ければいいですか?
A発疹の場所や喉・舌の状態に違いがあります。手足口病は手・足・口に発疹、ヘルパンギーナは喉の奥に水疱、溶連菌感染症は全身の細かい発疹といちご舌が特徴です。
Q溶連菌感染症ではなぜ抗菌薬が必要なのですか?
A原因が細菌(A群溶血性レンサ球菌)だからです。抗菌薬をきちんと内服することで合併症を防ぎ、再発を防止することができます。
Q手足口病やヘルパンギーナは薬で治りますか?
Aこれらはウイルスが原因なので特効薬はありません。治療は対症療法が中心で、解熱剤や鎮痛剤を使いながら自然に回復を待ちます。
Qこれらの病気に大人もかかることはありますか?
Aはい、大人も感染します。特に子どもから家庭内でうつることが多く、症状が強く出る場合もあるため注意が必要です。
Q登園・登校の目安はどのように考えればいいですか?
A手足口病とヘルパンギーナは、熱が下がり食事や水分が摂れる状態になれば登園可能です。溶連菌感染症は抗菌薬を開始して24時間以上経過し、解熱していれば登園・登校できるのが一般的な目安です。
まとめ:子どもの夏の感染症は迷わず相談を
手足口病、ヘルパンギーナ、溶連菌感染症はいずれも子どもに多い夏の感染症です。発熱や喉の痛みなど似た症状が重なるため、保護者にとっては判断が難しいことも少なくありません。特に溶連菌感染症は抗菌薬による治療が必要になるため、早めに見分けて対応することが重要です。
ただ、家庭での観察だけで「どの病気か」を正確に判断するのは簡単ではなく、登園・登校の可否や治療の必要性に迷う場面も多いものです。
そんな時に頼りになるのがオンライン診療アプリ「みてねコールドクター」です。
- 24時間365日、最短5分で医師の診察を受けられる
- 薬は近隣の薬局で受け取れるほか、全国配送(北海道、沖縄県、離島を除く)、一部地域では即日配送にも対応
- 登園・登校に必要な診断書や登園許可証の発行が可能
- システム利用料は無料で、健康保険や子どもの医療費助成制度にも対応
「みてねコールドクター」のアプリをインストールすれば、保護者の不安を軽減しながら、お子さんの健康を安心してサポートできます。あらかじめご家族の情報を登録しておけば、いざという時にスムーズにご利用いただけます。
家族のお守りに、みてねコールドクターをぜひご活用ください。
公式サイトはこちら:https://calldoctor.jp/