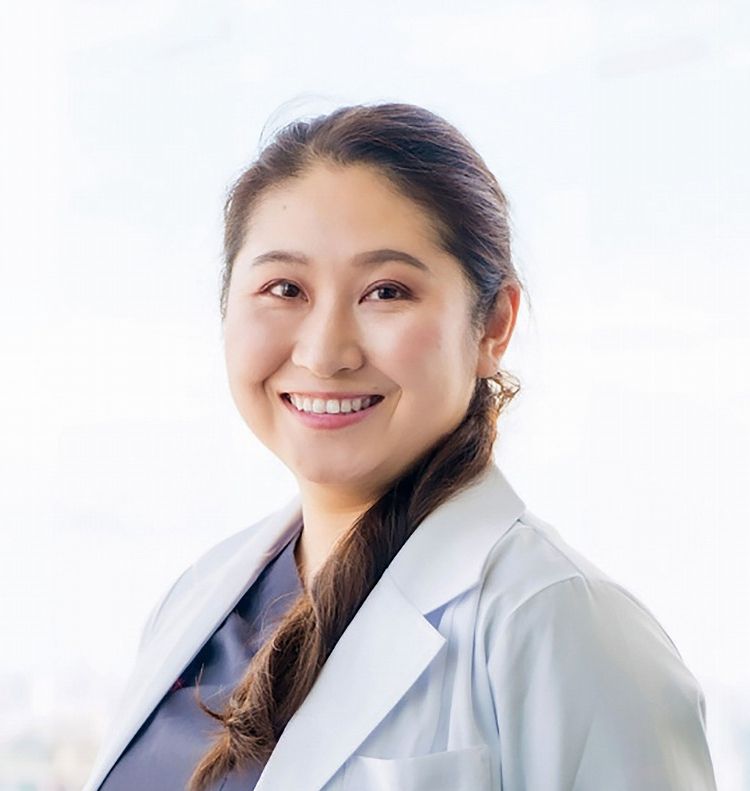子どもが風邪をひいた時の食事は? 小児科医がすすめる食べ物と飲み物

子どもが風邪をひいたとき、保護者として真っ先に気になるのが「何を食べさせればいいのか」ということではないでしょうか?
発熱や咳、鼻水などの症状があると、普段元気な子どももぐったりとして、食欲が落ちてしまうことは珍しくありません。「栄養のあるものをしっかり食べさせなきゃ」と思う反面、無理に食べさせることがかえって負担になるのではと悩むこともあるでしょう。
本記事では、小児科医の視点から、子どもが風邪をひいたときにどのような食事を用意すればよいか、体調や食欲に応じた食べ物と飲み物の選び方をわかりやすく解説します。症状ごとのポイントや回復に向けた食事の工夫、さらには薬との関係にも触れながら、子どもの体と心に優しい食事ケアについて詳しくご紹介します。
Contents
子どもの風邪と食事の基本ポイント
風邪をひいた子どもには、普段とは異なる食事の配慮が必要です。ただ栄養を摂らせるというよりも、体調や症状に合わせて「何をどう食べるか」が大切になります。とくに発熱や下痢、嘔吐がある場合には、体が水分や栄養を失いやすく、いつも通りの食事がかえって体の負担になることもあります。
このパートでは、まず「風邪の時に食事がなぜ重要なのか」をわかりやすく説明し、次に小児科医がすすめる基本的な考え方や対応の原則をご紹介します。無理に食べさせるのではなく、子どもの様子を見ながら、自然な形で回復をサポートする食事のあり方を考えていきましょう。
風邪の時に食事が大切な理由とは?
子どもが風邪をひいたとき、身体はウイルスと戦うためにたくさんのエネルギーを消費します。この時期は、栄養バランスの良い食事が免疫力の維持や回復を助けるうえで重要な役割を果たします。特に、発熱や下痢などの症状がある場合、体内から水分やミネラルが失われやすくなります。これを補うためにも、食事や飲み物による水分・栄養補給が欠かせません。
一方で、体調が悪いと食欲が落ちて、食事そのものが負担になることもあります。このため、無理に食べさせるのではなく、子どもの様子をよく観察しながら、食べやすく、消化に良いものを選んで与えることが大切です。つまり、風邪の時の食事は「栄養をとらせること」だけが目的ではなく、「体の状態に合わせたサポート」として捉える必要があります。
小児科医がすすめる食事の3原則
風邪をひいたときの子どもの食事には、押さえておきたい基本の三原則があります。
-
水分をしっかり補給すること
発熱や下痢、嘔吐によって体内の水分が失われると、脱水状態になりやすくなります。そのため、食事よりも先に水分補給を優先することが重要です。特に経口補水液やスープなど、水分と電解質を同時に補えるものが効果的です。 -
消化に良いものを選ぶこと
風邪のときは胃腸の働きも低下しているため、脂っこい食事や繊維の多い食材は避け、やわらかくて消化しやすいものを選びましょう。おかゆ、煮込みうどん、すりおろしりんごなどは、体に負担をかけずに栄養を摂るのに適しています。 -
無理に食べさせないこと
子どもが食欲を示さないときは、体がエネルギーを節約してウイルスと戦っているサインとも言えます。無理に食べさせると逆に消化器に負担がかかることもあるため、「少しでも食べられたらOK」と考えて、子どものペースに合わせる姿勢が大切です。
症状別|食べやすい食材と食べ方のコツ
子どもが風邪をひいたときの体調は一様ではなく、症状の強さや種類、回復のスピードも個人差があります。そのため、風邪の経過に応じて、食事の内容や食べさせ方を柔軟に調整していくことが重要です。特に発熱しているときや嘔吐・下痢があるときには、消化機能が低下し、食事が負担になりやすくなります。一方で、回復期にはエネルギーや栄養素の補給を意識した食事にシフトしていく必要があります。
このパートでは、風邪の症状に応じて、どのような食べ物や飲み物が適しているのか、また避けた方が良いものは何かを具体的に紹介します。お子さんの状態をよく観察しながら、体にやさしく、無理のない形で栄養を届ける工夫を一緒に考えていきましょう。
発熱・食欲不振の時に与えたい食べ物と飲み物
高熱が出ている時や体がだるそうにしている時は、無理に食べさせることはせず、水分補給を最優先にしましょう。特に子どもは体が小さく、水分の損失による脱水が進みやすいため注意が必要です。食欲がまったくない時期は、食事よりも「飲み物」での栄養と電解質の補給を意識しましょう。
下記は、発熱時や食欲不振時におすすめの飲み物・食べ物の一例です。
| 状況 | おすすめの飲み物 | おすすめの食べ物 |
|---|---|---|
| 発熱・ぐったりしている | 経口補水液、白湯、麦茶 | すりおろしりんご、ゼリー、プリン |
| 食欲が少しある | 味噌汁の上澄み、野菜スープ | バナナ、お粥・薄いパン粥 |
「冷たいものは風邪によくないのでは?」と思われがちですが、発熱時には口当たりのよい冷たいものが安心材料になることもあります。ただし、極端に冷たいものや、炭酸・酸味の強いものは避けたほうがよいでしょう。
また、食べられないこと自体を過度に心配せず、「少しでも口にできたらOK」という気持ちで見守ることが大切です。
嘔吐・下痢時に注意すべき食材と補給方法
嘔吐や下痢があるときは、胃腸が非常に敏感な状態になっているため、とにかく消化に負担をかけないことが最優先です。まずはこまめな水分補給を行い、吐き気や下痢が落ち着いてから、段階的に食事を再開していきましょう。
状態が落ち着いてきたら、野菜スープの上澄みやよく煮込んだおかゆなど、液状または半固形の柔らかい食事から少しずつ始めるのが良いでしょう。目安は「食べられそうな時に、少量をこまめに」です。
回復期におすすめの栄養補給ごはん
熱が下がって元気が出てきたら、徐々に通常の食事に近づけていく段階です。回復期では、エネルギー補給だけでなく、風邪で消耗した体力を取り戻すためのたんぱく質やビタミンを意識して取り入れます。
たとえば、以下のような組み合わせが回復期に適しています。
| 食材 | メニュー例 |
|---|---|
| 鶏のささみ | ささみ入りおじや、スープ煮 |
| 卵 | 卵とじうどん、炒り卵、茶碗蒸し |
| 白身魚 | ほぐしておかゆに混ぜる、蒸し焼き |
| 柔らかく煮た野菜 | にんじん、かぶ、ブロッコリーの穂先 |
子どもが風邪の時に避けたい食事・飲み物
風邪をひいている時の子どもにとって、食事は回復を助ける大切な要素である一方、内容によっては逆に症状を悪化させてしまうこともあります。体が弱っているときには、胃腸の働きが落ちているだけでなく、喉や消化器も敏感な状態になっています。普段は問題ない食材や飲み物でも、風邪のときには負担になることがあります。
このパートでは、風邪の時期に避けるべき食べ物や飲み物について、具体的にご紹介します。
胃腸に負担をかける食材とその理由
特に注意したいのは、「元気になってきたから、もう何でも食べられるだろう」と急に通常食に戻してしまうこと。胃腸の回復にはタイムラグがあるため、見た目の元気さよりも内臓の回復を意識し、ゆっくり戻しましょう。
以下に挙げるような食品は、風邪の時期には避けた方が良いとされています。
| 食材カテゴリ | 理由 |
|---|---|
| 揚げ物・脂っこい料理 | 油分が多く、消化に時間がかかるため胃に負担をかける |
| スナック菓子や加工食品 | 塩分・添加物が多く、栄養価が低い。のどの渇きを促進することも |
| 食物繊維が多すぎる食材(ごぼう・きのこ・こんにゃくなど) | 胃腸の動きを促進しすぎて、下痢や腹痛を誘発する恐れがある |
| 冷たすぎる食べ物 | 胃腸を冷やして消化力を落とすことがある |
喉の痛みを悪化させる飲み物とは?
代表的な注意すべき飲み物は次の通りです。
| 飲み物 | 注意点 |
|---|---|
| 柑橘系ジュース(オレンジ、グレープフルーツなど) | 酸味が強く、喉の粘膜を刺激する |
| 炭酸飲料 | 炭酸の刺激が咳を引き起こすことがある |
| 乳製品(牛乳・ヨーグルトなど) | 体調によってはお腹をゆるくし、痰が絡みやすくなる |
| 極端に冷たい・熱い飲み物 | 喉や胃腸を刺激してしまうため避けるのが無難 |
食事と薬の関係|知っておきたいポイント
子どもが風邪をひいたとき、食事と並んで気になるのが「薬の飲ませ方」です。食欲がない、苦い薬を嫌がるなど、与え方に悩むことも多いはず。ここでは、薬と食事の関係について基本を整理します。
薬を混ぜていい食べ物・避けるべきもの
とくに避けたい組み合わせの例
| 食べ物・飲み物 | 避ける理由 |
|---|---|
| ヨーグルト、牛乳などの乳製品 | 一部の抗生物質と反応して吸収が悪くなる可能性 |
| オレンジジュースなどの酸性飲料 | 苦味が強調・成分が不安定になる可能性 |
| 熱すぎる食べ物 | 成分変化や味変化の可能性 |
一方、バナナすりつぶし、プリン、アイスクリームなどは混ぜやすい食品の例です。ただし薬により可否が異なるため、必ず薬剤師に確認しましょう。
食事がとれない時の薬の飲ませ方
小児で処方される薬の多くは、食事が少なくても服用できる設計ですが、全てではありません。空腹時に刺激の強い薬もあるため、医師・薬剤師の指示を確認してください。
食べられない時は、少量の水分を先に与える/服薬補助ゼリーを活用するなどで負担を減らせます。
栄養と免疫力を支える家庭ケアの工夫
症状対応と同時に、「次に風邪をひきにくくする」視点も大切。特別なサプリより、毎日の食事の工夫が土台になります。
免疫を助けるビタミン・栄養素の摂り方
以下は、免疫力アップに役立つ栄養素と代表的な食材の組み合わせです。
| 栄養素 | 役割 | 含まれる代表的な食材 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 白血球の働きを活性化、抗酸化作用 | いちご、みかん、ブロッコリー、ピーマン |
| ビタミンA | 粘膜の強化、ウイルスの侵入防止 | にんじん、かぼちゃ、レバー、卵 |
| たんぱく質 | 免疫細胞の材料 | 鶏肉、魚、豆腐、納豆、卵 |
| 亜鉛・鉄分 | 免疫細胞の活性化 | 赤身の肉、レバー、あさり、ひじき |
※ビタミン・ミネラルは日々少しずつ・バランスよくが基本。発酵食品(ヨーグルト、みそ等)で腸内環境も整えましょう。
日常の食生活でできる風邪予防とケア
- 朝食は必ずとる:体温を上げ免疫を活性化
- 甘いお菓子やジュースを控える:糖分過多は免疫低下の一因に
- 旬の野菜・果物を活用:ビタミン・ミネラルを自然に補給
- 体を冷やさない:お腹・足元を冷やさない服装と寝具
- 食への興味を育てる:一緒に料理・盛り付けなどで「食べる楽しさ」を
よくある質問
Q子どもが全く食べないとき、何時間くらい様子を見ても大丈夫ですか?
A食欲が一時的に落ちるのは風邪の自然な経過としてよくあることです。水分がしっかり摂れていて、元気があるなら、丸1日程度は無理に食べさせず様子を見て大丈夫です。ただし、ぐったりしていたり、水分もとれない場合は、早めに医療機関に相談してください。
Q経口補水液とスポーツドリンクの違いはなんですか?
A経口補水液は脱水時の水分・電解質の補給を目的とした医療的な飲料で、ナトリウムなどの電解質濃度が高く設計されています。一方、スポーツドリンクは運動時の水分補給用であり、糖分が多めです。風邪の時は経口補水液の方が適しています。
Q薬をプリンやアイスに混ぜても大丈夫ですか?
A薬の種類によっては問題ありませんが、薬によっては効果が弱くなる場合もあるため注意が必要です。事前に薬剤師に確認するか、処方時の説明書をよく読みましょう。プリンやバニラアイスは比較的混ぜやすく、子どもが飲みやすいことが多いです。
Q風邪のときにヨーグルトは与えてもいいですか?
A症状によります。下痢がある時やお腹がゆるい時は避けた方が無難です。逆に、症状が落ち着いていて、食欲が戻ってきたタイミングであれば、腸内環境を整える食品として役立つこともあります。
Qどんな食べ物から回復食に戻せばいいですか?
Aまずはやわらかく消化の良いおかゆや煮込みうどんなどがおすすめです。そこから、鶏ささみや豆腐、卵、白身魚などの良質なたんぱく質を少しずつ取り入れていくと、体力の回復をスムーズにサポートできます。
Q熱が下がったあとも食欲がないのは大丈夫?
A熱が下がっても、体の中はまだ回復途中であることが多く、食欲が戻るには少し時間がかかることもあります。水分が摂れていて、元気があるようであれば、無理に食べさせず、少しずつ食べられるものを増やしていきましょう。
Q風邪のとき、ビタミン剤やサプリメントを使ってもいいですか?
A特別な栄養補助が必要な状況でなければ、基本的には食事からの栄養で十分です。サプリメントを与える際は、医師に相談してからにしましょう。一方、旬の果物や野菜から自然にビタミンを摂るのはとても効果的です。
Q食事だけでなく診察のタイミングも迷ったらどうすればいい?
A判断がつかない時は、すぐに医師に相談するのが最も安心です。自宅から相談できる「みてねコールドクター」なら、24時間365日対応、最短5分で診療可能。登園許可証や診断書の発行、薬の手配もできるため、急な症状にも安心して対応できます。
まとめ|食べられるものを大切に。困ったらみてねコールドクターへ
風邪の時期の食事で大切なのは、水分優先・消化に優しい・無理をしないの3点。子どもの様子を見ながら「少しでも食べられたらOK」の姿勢です。
症状対応や受診タイミングに迷ったら、オンライン診療アプリ**「みてねコールドクター」**が心強い味方です。
- 24時間365日、最短5分で医師の診察
- 薬は近隣薬局受け取り・全国配送(北海道、沖縄県、離島を除く)・一部地域は即日配送
- 登園・登校の診断書や登園許可証の発行に対応
- システム利用料無料、健康保険・子どもの医療費助成制度に対応
家族のお守りに、みてねコールドクターをぜひご活用ください。
公式サイト:https://calldoctor.jp/